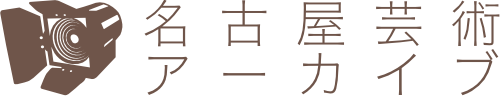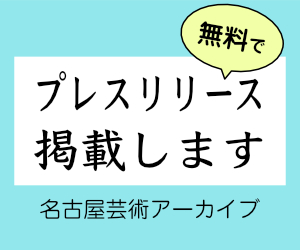その先に
まずは鳴海さんが演劇を始めたきっかけを教えてください。
■鳴海康平さん(以下鳴海):高校時代は医者を目指してまして、完全な理系だったんですよ。それが高校三年生の春過ぎくらいに学力上の問題に突き当たりまして、もう無理だとで諦めてからは、しばらく学校さぼって公園で絵を描いたりとかしていたのですが、秋くらいに学校祭がありまして、その中でクラスでつくる出し物があったんです。その時、私が、演出というのはおこがましいですけど、5分くらいの出し物を演出して、そのときに表現するというか、創造するというのは面白いなと思ったんです。それから映画とか演劇の表現というものに興味を持って、それ以降、進路を考えた時に、早稲田に演劇の勉強できるところがあることがわかり、進学したんです。
最初は演劇だけではなく、映画制作も視野に入れていたのでしょうか。
■鳴海:はい。それが大学の学生演劇サークルに入ってどっぷりハマり、大学一年目の5月を越えた辺りから授業に行かなくなっちゃいまして。それからずっと演劇漬けになってしまいましたね。映画より断然こっちのほうが面白いと。
そこから『第七劇場』を立ち上げるまでの経緯を教えてください。
■鳴海:私が入った学生劇団の中でユニットをつくって演劇祭みたいなのをやろうってことになって。それが最初のきっかけで、そこから自分の劇団を、そのユニットを基盤にして設立したんです。
演劇サークルが母体になって、そのまま。
■鳴海:そうですね。同じ学生劇団にいた面子の何人かと一緒に作ったのが最初ですね。
『第七劇場』という名前の由来を。
■鳴海:一番最初は『eggflip』という名前でつくったんです。2004年に改称しました。その時に第七劇場という名前を付けたんです。最初のeggflipという名前は辞書をめくって適当に「これ」って決めた名前だったんですね。でも私が作る作品というのは大抵ちょっと暗い質感で、名前が可愛い割に作品が暗いのはずっと気にかかってたんです(笑)。また、eggflipという名前からだとその劇団の演劇スタイルというのが想像しにくいので、あまりかわいい色がつかない、イメージが偏らない名前にしようと思って。まず芝居をやってるので「劇場」という単語を使い、後は数字を使って、あまり色づけをしないように。「第七」というのは、語呂もいいなと思ったんですけど、地球上には大陸が六つしかないので、その先に、という意味で「第七」。第七劇場。
色々な表現のメディアがある中で、鳴海さんが演劇を選んだのは何故でしょうか。
■鳴海:最初は自分のいる世界を理解する為に演劇を続けていた節があるんですが、何故演劇を辞めずに続けているかと考えると、演劇というのは人に近い芸術とか、人と人が深いコミュニケーションを取る芸術だと感じていて、例えば映画とか小説とかだと、紙とか銀幕を介してお客さんと繋がるんですが、舞台芸術は、生身の人間であるお客さんに、生身の人間を通して見せる、とても人間臭い表現。芸術と呼ばれるものの中ではちょっと珍しい。人間という不完全で、面倒臭く、不可解なんだけど、そういった関係の中に居続けられる、それが演劇の醍醐味だな。そしてそれが凄く興味というか、自分にフィットするので、演劇を続けている、というのがありますね。
人と直接やり取りできるのが魅力。
■鳴海:そうですね。社会生活をしていくと、段々麻痺してしまう部分というのは現代にはもの凄く多くあると思うんですね。色んな情報に隠れてしまっているものとか。色んな人間関係の中で、深く付き合うことをせずに過ごしていける。色んな部分が麻痺したり、慣れてしまう。でも演劇の世界にいると、それでは済まされなくなってくるんですね。汚い部分と奇麗な部分をひっくるめて見続けないといけないので。
人とやりとりするうえでしんどくなることはありませんか。
■鳴海:いやあ、ありますね(笑)。特に、劇団ということで言うと、人間関係とか、コミュニケーションを取ることがもの凄く時間もかかるし、手間もかかるし、労力もかかる。確かに凄く大変なことだと思います。だけどそれがあるからこそ、人間が一緒に成長していけます。奇麗な部分とか、肌触りがいいだけの関係でない部分に演劇の魅力があって、それに私は強く惹かれるので。逆説的ですけどね。もの凄く苦労はしますが、そこに生きてる感じがするんです。もう私にとっては劇団員は、質や形の違いはあれ、家族のように感じています。とても個性豊かすぎますが(笑)。
アフリカの原住民にとって全然関係ないこと
能や歌舞伎、舞踏やコンテンポラリーダンスなどを取り入れた作品を製作しているということですが、それらと演劇との融合に関し、うまくいっている部分と苦労している部分を教えてください。
■鳴海:eggflipを立ち上げた時に、自分でも脚本を書いていたんです。でも、自分で書くことに関して、自分の才能の限界を感じたという部分もあるんですが、今までの劇作家の作品を読むと、膨大な知識であったり知恵であったり、そうしたものを元にして書かれていて、私が書くのはおこがましいと思ったんです。そこで演出というポストに専念しようと考えたんです。もちろん、劇作家より演出の方が簡単というつもりはなくて、演出っていう漠然としたポジションを自分なりに築くことに興味を覚えたんですね。また、書かなくなった理由のひとつとしてリアリズムと呼ばれる演劇に対する限界を個人的に感じた。そこで身体表現というものにも少しバランスを置いて、演劇を製作しようかなと。
何故そこで身体表現に注目されたのでしょうか。
■鳴海:演劇っていうものをやる以上は、国境も時代も越えられる作品を作りたいと思ったんです。もちろん映画とか小説とかというのも、時代を越えて存在するものなんですけど、演劇というのは国境を越えられない部分が多々あるので。それは何故かと言うと言語の問題があるんですね。映画や小説には字幕とか翻訳とかあるかもしれないけど、演劇に関しては今までの歴史を見ても、うまく共存できていないんですね。翻訳で言語を越えた作品は、元の母国語との関係が言語レベルでうまく成立してないのは歴史が証明しているので、言葉だけに頼らずどうやって芝居を作ろうかと考えた時に身体性というのが出て来たんです。そして身体性というものに注目すると、日本の伝統芸能の能や歌舞伎はもちろんはずせなくなってくるし、ダンスというものもひとつの身体性の形としてありえる。それらとどうやったら共存できるかを考えているんですけど、身体性という枠組みで言えば色々と共通するものがあるので、お互いがお互いを支え合えたり引き立て合えたり相乗効果を生み出したり、言葉ではない部分で刺激しあえる部分があるというのがうまくいってるというか、興味深い。まだはっきりと自分の中で掴めていないのは、演劇は言葉を発しているので、身体表現と言葉の間の溝の関係性をどう処理していけばいいのか。その辺はまだまだ可能性に悩むところですね。
リアリズムに限界を感じたというのは、なにかきっかけがあったのでしょうか。
■鳴海:戯曲の名作とされているものには、もちろんリアリズムの劇もあるんですけど、圧倒的に単純なリアリズム劇として書かれているものよりも、書かれていないもののほうが多いんです。それと、日本の歴史で言えば、明治以降、ロシアから輸入された歪んだリアリズム演劇というのは、海外で評価を受けたことがほぼ、ない。それって何故だろうってという風に考えることがきっかけだった。作品が国境を越える、時代を越える為にはどんな可能性があるかって考えた時に、例えば私たちが今こうやって思っていることは、アフリカの原住民にとって全然関係ないことなんです。同じ国だったとしても、江戸時代の心理と今の私たちの心理は違う。ということは、情、心理というのは必ずしも普遍的ではない。言葉を母国語から翻訳する時に抜け落ちてしまうことを考えても、言葉というものが普遍的じゃない。となるとリアリズムの演劇というのは普遍的じゃないんじゃないか。私の作品にはアフリカの原住民に観せたとしても、江戸時代の人に観せたとしても、なにか面白く応えるような普遍性を求めたい。国境も時代も越えられるような作品。その辺を考えたのが、心理主義的なリアリズム演劇にひとつの限界を感じた理由です。
普遍性を獲得する為に、身体表現以外で意識していることはありますか。
■鳴海:普遍性というところを意識すると、個人。個人イコール孤独。個人が孤独とどう向き合うかという作品というのが普遍性を獲得して時代を越えられるんじゃないかなあと思っています。名作と呼ばれてきたもの、受け継がれてきたものは、大抵の場合、個人の孤独との葛藤であったりとか、それでどうやって生きていくか、どうやって処理をしていくかということを突き詰めて考えていった結果、そういう作品になったというのが多いように思う。誤解を恐れずに言えば人間という存在自体は普遍的なものですから。人間自体が抱えている、普遍的な孤独というのは今も昔も変わらない。それを扱う作品というのは普遍性を獲得すると思う。
今後の作品でそういったものを扱いたいと思いますか。
■鳴海:もう私は自分では本を書かなくなっていますけど、どうしても私の中では作品の中に普遍性だったり、孤独であったり、そういうものをどうやって明らかにするかということを考えながら演出をつけているので、できる限り普遍性は獲得していきたいと思います。
ひとつの時間の中に複数の空間を封じ込める
演劇独特の表現を目指しているとのことですが、演劇にしかないような表現はありますか。
■鳴海:ひとつの時間の中に複数の空間を封じ込めることができるのが、演劇独特の、舞台芸術独特のものですね。例えば、映画やテレビはフレームの中にあるものが基本的に事実として受け止められる。だから部屋の中でひとりの男の人が喋っていると、それは全て事実として受け止められる。演劇の場合はそれが部屋の中だったしても、どう演技するかによってそこが部屋じゃなくなることがあるんです。部屋になったり海になったり空になったりすることができる。それは言ってしまえば凄く簡単なことかもしれないけど、他の芸術ではなかなかできない部分。ある特定の仕掛けをしっかり作らないと演劇以外ではなかなかできない。それはひとつ長所ですね。あとは、ちょっと生々しいですけど、俳優がその気になれば客席に降りてお客さんを殴ることもできるし、逆にお客さんが本気になれば、舞台に上がって俳優を殴ることもできる(笑)。それって凄く大事なことで、お互いを目の前にしているという緊張感がある。テレビや映画で女優さんが泣き喚くシーンを観るのと、舞台で同じシーンを観るのでは生身の緊張感が全然違う。それはやっぱり舞台芸術のひとつの長所ですよね。
鳴海さんはプロフェッショナルであるという部分を大事にしているように感じるのですが、プロフェッショルとして大事なことはなんでしょうか。
■鳴海:演劇の先進国と言われる国の演劇人、舞台で活躍する演劇人というのはすべからく皆文化人であるべきという意識を持っているんです。そういう態度であり意識であるというのは、なんにせよ。ヨーロッパの人たちが日本にやってきて「今面白い歌舞伎の演目はなんだ」と聞かれたときに答えられるような知識と教養をもつことは重要です。そういうのは日本の演劇人にはほぼないです。それは明らかに表現者としてはおかしいはずなんです。
役者に求めることはありますか。
■鳴海:同じく文化人であるべきだと思う気持ちは同じ。後は俳優というのは身体をどうしても使う。最後に舞台の上でお客さんに責任を取る、最終的なポジションですから。自分の身体、メンタルというものをきちんとコントロールできる能力というのはやはり必要なんじゃないでしょうか。言ってることはアスリートとほとんど同じなんです。精神的なところや身体的なところの向上を常日頃努力する。アスリートと同じです。
小児科医になりたかったんですよ
鳴海さんの行動の源には「罪と矛盾」があるということですが、それを意識されたのはいつ頃でしょうか。
■鳴海:暗いですね(笑)。色々な複合的な影響の中で最終的にそういう言葉になるんですけど、ひとつ大きなきっかけと言えば、祖母の死があります。私は98年に北海道から上京したんですが、ちょうどその年に実家で祖母が亡くなった。その祖母が亡くなって、実家に帰って、葬儀を済ませて遺体を焼く時に、自分では信じられないくらい涙が出て、それはもう自分の理解を越えた身体の反応だったんです。それがひとつ自分の中の変化を起こした気がします。直接的に罪と矛盾に関わることではないですけど、人ひとり、自分の肉親がこの世を去って、もう二度と会う事ができない、もう二度と身体に触れることも目を合わすこともできない。でも私は生きていかなきゃならない。私もやがて死ぬ。もの凄く大きな時間の流れというか、命の循環というものと自分というものを点として強く意識した契機として、そのときの流した涙というのは大きな影響があったと思います。
罪と矛盾というのは、なにに対する罪であり、矛盾なのでしょうか。
■鳴海:言葉が安くなっちゃうんですけど、生きているということの罪であり、生きていることの矛盾という面と、人間そのものが持っている罪であり、矛盾です。とても大きな流れの中で、点として私が持っている罪であり矛盾です。
演劇で最も表現したいことは。
■鳴海:生きる力というものですね。昔は家庭の中には親がいて、子がいて、おばあちゃんやおじいちゃんとか、兄弟とか、家庭の構成員数が多かったんです。その中で親とか学校は、現実的に生き延びる方法を教えてくれるんです。でもおじいちゃんおばあちゃんというのは、経済的に生きる為の力はくれない。生きる為には必要ないようなことを教えてくれるんですね。でもそれってもの凄く大事なことで、人生に頓挫した時に必要になってくるのは、極端なことを言うとおじいちゃんおばあちゃんに教わったような、現実的に生き延びる為には一見必要のない力です。お化けの話だったりとか、迷信の話だったりとか、遠く離れたところにある、自分の理解できないこと。それは現実的に経済的に生きる力ではないかもしれない。でも生き抜く力として自分に備わってる部分があるんです。
生き抜く力。
■鳴海:そういう意味で生き抜く力、生きる力をどんな形であれお客さんに与えられるようなものを作りたい。高校時代、私は小児科医になりたかったんですよ。それは何故かと言うと、子供って何になるか分からないじゃないですか。その子がヒトラーになるかもしれないし、アインシュタインになるかもしれない。それは分からない。分からないけど、そこで命を潰してしまうのはあまりにも痛ましい、という気持ちがあって、それに代わるようなことを演劇でできないかと悩んだんです。芝居を観て、死にたくなるとか、そういう部分もあるかもしれない。そういう可能性がない訳でもない。でも自分がこれから先生きていくということに関して、なにかしらの刺激を与えられるような作品を作りたいです。
その刺激が、おじいちゃんおばあちゃんの知識のようなものなんですね。
■鳴海:そうですね。どんな言葉を並べても演劇で命は救えないんですよ。戦争も止められないし、ガンもエイズも治せない。ではなにが出来るんだろうか。現実的に生きるってことは学校でも教えてくれる。そうじゃなくて、そこでは補い切れない余計な知識であるとか、言葉が大仰ですけど、大いなる無駄、そういった余白の部分っていうのを人間は持たないと、壁にぶつかったときに止まるんですよね。止まってもいいけど動けなくなる。そこから前に進む、動き出す為には無駄であったり余白であったり、そういうものが必要なんじゃないかなあと。
言葉の意味とは離れた部分を表現していく
第七劇場の見所を教えてください。
■鳴海:言葉の意味に縛られない表現というもの大切に作品を製作していきたいですね。お坊さんが念仏を唱えている時、念仏の意味は分からないけど、凄く神々しかったり有り難かったり、なにか神懸かり的なことがあったりしますよね。言葉の意味の部分ではないところに共感したり、そういった部分を追求していきたいと考えています。オリジナリティとまで言えるかどうかはまだ自分の中では分からないですが、そういった部分はひとつ見所だと思います。
五感全てで感じるようなものを創る?
■鳴海:そうですね。
触感にも訴える部分はありますか。
■鳴海:生身の人間がそこにいるという緊張感とか気迫であったりとか、呼吸であったりとか、そういうものは目で見るよりは肌で感じる部分なんですね。そこは触感として占めるべきところですね。肌で観れる。
俗っぽい言い方になりますが、オーラのようなものを作ろうとしているのでしょうか。
■鳴海:ある意味、そうだと思います。言葉の意味ではない部分。言葉にできないことを言葉にするのは難しいですが。オーラであったり、雰囲気であったりとか、気分とか、そういう言葉で言われることが多いと思いますが、ある種、言葉で言いようのない部分を指す為に使われる言葉なんですね。言葉を意味として、話の流れとして大事にしてる部分はあるんですが、それだけではなくて、その外側、内側にも存在しているような肌で感じたり、言葉の意味とは離れた部分を表現していくことを大事にしたい。そこを是非味わっていただきたいなと。
結局のところ、劇場に行って感じるのが一番分かりやすいんですね(笑)。
■鳴海:それが一番なんだと思います(笑)。昔はお寺や神社なんかに人が集まって、そこで勉強するとか、噂話があったりとか、仏教があったりとか儒教があったりとか、お寺や神社に多くの知識やコミュニケーションが集まった時期がありました。そういう存在でありたいと思います。単純にお話を伝えるだけのものではなくて、学問としての側面もあるかもしれないし、生きる力としての側面もあるかもしれないし、言葉の意味だけではない、色んな形のコミュニケーションを取れるようにしたい。
まだまだお話したいのですが、あまり長くなるのも悪いですので。よかったら今度またお話させてください。今日は本当にありがとうございました。
■鳴海:こちらこそ、ありがとうございました。