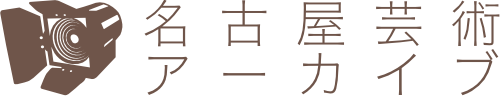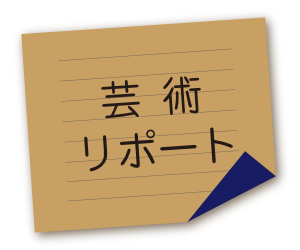アングラみたいなことやっていました
松井さんが演劇を始めたきっかけを教えてください。
■松井周さん(以下松井):高校の時に演劇部に入ったんですけど、好きな子が出来て、その子が演劇部に入るって聞いたので、それにほいほい付いて行ったってだけなんです。だからその時はそんなに演劇がやりたかったのかどうかは分からないんですけど、凄く軽い動機ですね(笑)。でもその子は入った途端に出て来なくなって、幽霊部員になっちゃって、ぼくは結構真面目にやってたんですけど。だからそれがきっかけですね。
好きな子がすぐ幽霊部員になっても辞めなかったのは何故ですか。
■松井:だって、ぼくもすぐ辞めちゃったら相当恥ずかしい(笑)。なにこいつって。だからやろうと思って。でもまあ演劇も好きだったので。でもその頃は『キャラメルボックス』とか日本の劇作家の演劇をやっていたんですけど、ぼくは姉が大学でやっている『ガラスの動物園』という英語劇を観て、それが高校で出来ないかなと思っていました。それを楽しみにやっていた。高2くらいで実際やったんですけど。それから明治学院大学って大学に入り、演劇サークルがあったのでそこに入って。そしたらそこの先輩が寺山修司とか唐十郎が好きな先輩でして、その人の影響の元にアングラっぽい芝居を始めて。観に行くのも『唐組』とか『新宿梁山泊』とか。もうほんと水被ったり唾飛ばしたり、走り回るような演劇。それでぼくも白塗りしたり。学内の中でチラシ配るのもスローモーションで黒いマント着て、人形のように配るとか。誰も受け取ってくれなかったですけど。モロそういうのにかぶれて。そういうアングラみたいなことやっていました。
そこからサンプル立ち上げまでを教えてください。
■松井:大学卒業して『青年団』に入りました。そこで10年くらい俳優をやって、今も所属していますけど、30くらいで戯曲を書いて。青年団入った頃からずっと書きたいと思ってたんですけど、書き上げることが出来なくて。これじゃ駄目だと思いながらも。そして10年経って初めて書いて、それを劇作家協会の新人戯曲賞に応募して。もしそれに何もひっかからなかったらもう書かなかったと思うんですけど、最終ノミネートに入ったので。そしてそれを実際上演してみたかったし、もうちょっと演劇をちゃんとやろうと思って、演出をやるようになって。それを3年ぐらい青年団の若手自主企画としてやってたんですけど、2007年に青年団からは独立した形で、自分の劇団『サンプル』を立ち上げました。
これを果たして自分に出来るのかな
30で初めて戯曲を書かれた。
■松井:いやでもほんとに書けないと思ってましたけどね。平田オリザの戯曲を真似して何度も書こうと思ってたし、あの人は『創作』というワークショップをやっていまして、それは15分くらいの短い芝居をグループで作るというワークショップ。それのやり方を頭に叩きこんで、その作り方で戯曲を書いたりしてたんですけど、これがオリジナルとは思えなかった。でもふとしたきっかけで、今まで書いてきたものだと埒があかないので、ある地点から確率の低い方、低い方へ物語を進めてみようと思って書いてみたんですね。例えば喫茶店である二人が居て、普通に話してるんだけど、一方が一方に突然水やコーヒーをぶっかけたらどういう風に会話は進むんだろうと。とにかくそういう行動を起こさせてみて、その後の会話を考えてそれで書いてみるというのをやったら、自分が書いてて楽しくなったので書き進められて。
現在でもその手法は使われているのでしょうか。
■松井:そうですね、基本的には。でも、それをやることでぼくの作品はめちゃくちゃになっているというのはある(笑)。
アングラから青年団に行かれたということですが、真逆に行かれましたね。
■松井:唐さんとかを観ていて、椅子は無くてもいいとか、台詞は聞こえなくてもテンションや熱気で伝えるとか、俳優が客席もどこも関係無く走り回るとか、あとは屋台が崩れて俳優が池に飛び込んでいくとか、そういうある種事件というかハプニングのような演劇って面白いなと思っていたのですが、観に行くと毎回同じことやっていて。それで「あれ」って思った。拍手とか起きちゃってて、これはいつもの催しなんだなと思って。もちろん面白くあったんですけど、それほど衝撃的でも無くなった頃に青年団を観たので。青年団は真逆の意味で今までいわゆる新劇的なストレートプレイに見えながらも台詞が正面を向かないとか、台詞が凄い重なっているとか、人間をもっと俯瞰で見ている感じがしたんです。新劇はもっと人間に寄り添うイメージ。分かりやすく真理を演劇的に表現して、分かりやすく見せている芝居だとしたら、もうちょっと俯瞰というか監視カメラで見ているような。そういう作り方が今までの演劇と似ているようで違ったというのがあって。じゃあこういう世界はどうやって作られているのかなって。これを果たして自分に出来るのかなって思った。
価値が全てひっくり返るという感覚
これまでに松井さんが影響を受けた作品や人物がいれば教えてください。
■松井:楳図かずおさんですね。楳図かずおさんと大江健三郎さんと、深沢七郎さんはいつでも読み返していますね。絵でいうと、バルトゥスとかブリューゲル、ボシュの絵とかはよく見ていますね。
楳図かずおさんの名が凄く引っ掛かるのですが。
■松井:楳図かずおさんは相当です。数日前も読んでました。
楳図さんの作品で特に好きなものはなんでしょうか。
■松井:たくさんありますけど、『漂流教室』は最初に読んだ作品で。小学生2、3年の時に読んだんですけど、小学生同士が殺し合いをしなきゃいけない状況とか、教室に閉じ込められて火を付けられてとか、息苦しくなるくらいにインパクトを受けた。それはただショックを受けたんじゃなく、今まで持っていた価値観が全てひっくり返される表現みたいな。子供のほうは環境に適応していくんですけど、大人のほうがおかしくなってしまう。その感覚というか。価値が全てひっくり返るという感覚を初めて味わった作品だったので。
何かに言葉を当て嵌めるという行為が凄く暴力的
自身の戯曲に関して、特徴や癖があれば教えてください。
■松井:さっきも話しましたけど、確率の低い方低い方に話が転がっていくという特徴があると思います。そこから来るのかもしれないですけど、ズームインして見れば整合性の取れる話なのに、俯瞰で見るとどう考えても辻褄が合わない作りになっていると思います。いくつかの物語のレイヤーが重なっているような作品なので。これは誰の物語なのかあやふやというか分からなくなってくる。これは一体どこでいつなのか。段々分からなくなってくる。
戯曲のアイデアはどういうところから生まれますか。
■松井:人間についてよりも、動物について考えたりしますね。例えば犬のブリーディングってあるじゃないですか。血統が良くて奇麗な毛並みに育てるよう、親と子を交尾させて掛け合わせる。それって血の繋がりの濃い掛け合わせばかりですけど、それをやってると障害を持って生まれてくる子供もいるので、逆にちょっと薄めてみるとか、外の血を入れてみる。そういう感覚で操作しているのを、人間に置き換えたらどうなるんだろうとか。人間の珍種というか、あまり滅多に生まれない人間のタイプを町起こしの為に作ろうとしている人々を物語にしてみたりとか。『自慢の息子』の場合は、自分に子供が生まれたのですが、子供に名前を付けるという行為、何かに言葉を当て嵌めるという行為が凄く暴力的に思えた。でもそれって、物語の初めというか。親の希望とか、将来いじめられないようにとか、占いで幸せになるようにとか、名前を付ける時点で物語を色々考えている。で、名前そのものにそれが込められているというのが面白いなと。じゃあ、そういうものを国に準えて、なんでもない土地に色んな名前を付けていく、それが暴力的というものに繋がらないかなと思い、なら、独立国を自分のアパートの中に作っている引き蘢りの男の話にしようと。でもその男の名前は母親が正しく生きるように『正』と付けたとか。そういう連鎖があるような感じですね。
演出をするうえで重視していることがあれば教えてください。
■松井:その空間とどれだけ関われるかということですね。俳優が座りながら喋るのか、寝ながら喋るのか、立ちながら喋るでもいいですけど、この空間に影響されている。この空間に入っているだけで。声の響きとかを無意識で計算しながら喋っている。このくらいだったら聞こえるかなとか、人との距離でもいいし、光の当たり具合とか、色んなことを受け止めながらそれに反応しているのが人間なんですけど、それをちゃんと表せられているかですね。
それは稽古場という空間のことなのか、芝居で設定された空間のことなのか、どちらのことを指しているのでしょうか。
■松井:そう、その二重性というのがちゃんと意識できているかですよね。例えば王様という役で、王様の王室ですという設定でも、ここは木の床で、この水銀灯の下でやらないといけない。どっちの要素もある。王様でいるという一種のフィクション。それは言葉を貼り付ける、物語を貼り付けることだと思うんですけど。俳優が王様という物語を貼り付けられるじゃないですか、だけどその人はその人個人であるということの二重性をちゃんと分かっているかどうか。で、この部屋はこの部屋であるんですけど、王室でもあるよと。そのフィクションとこの場とのブレンドが出来ているかどうか。舞台機構をそのまま見せている状態でも、丸っきり照明とかが見えている状態でも、「そこは海です」となった時に、俳優はバトン(照明などを吊る棒)とかをどう海と関連付けられるのか。海苔を干してる場所にするとか、それをちゃんと利用して、嘘付けているか付けていないかは別としても、ちゃんとブレンドして欲しい。
色んな所に跳ね返ってくれる俳優
一緒に活動するうえで相手に持っていて欲しい要素があれば教えてください。
■松井:共同作業なので、常識があるか、協調性があるかどうかというのもありますけど、ただその、ぼくが持っていて欲しいのは、感受能力。受け止める能力。よく言うんですけど、ピンボールってあるじゃないですか。スタートしてポーンと弾いたら、どんどん色んな所に跳ね返る。ひとつポーンと押しただけで色んな所に跳ね返ってくれる俳優。それって結構すぐ鈍ってしまう能力であって、それはちゃんと鍛えるというか、研ぎすまして錆びないようにメンテナンスするスキルじゃないかなと思うので。まずそういう才能として持っていて欲しいですけど。跳ね返る。そしてメンテナンスしている人という感じですね。
役者には台本の台詞をそのまま守って欲しいと考えていますか。
■松井:それで面白くなる分には台本を変えてもいいと思う部分もあるんですけど、ただ、リアリズムでうまく流れて行くのを欲していない時もたまにあるので。最近。逆に固い台詞を言いづらそうに言ってとか。台詞に酔って喋るというフィクションに入って欲しいとか。そういう風に注文することもあるので。ケースバイケースなんですけど。
演劇的な台詞。
■松井:そうですね。宝塚っぽく喋って欲しいとか。でもそれが宝塚調ですよっていうお客さんを安心させるように提示したいのではなく、物語の妄想をちゃんと生きて欲しいというか。そういうことでは出すのですが。真剣にそれをやって欲しい。ギャグとしてではなくやってもらう。
いくつもの物語を貼り付けていく
岸田戯曲賞を穫られた『自慢の息子』が、これまでの作品と大きく違った点、そして作品の注目点があれば教えてください。
■松井:大きく違う点は、台本がヒエラルキーの上にあって、ピラミッドの頂点にあるという感じで皆が動くという形が、なんとなく従来のスタイルだとしたら、台本も空間も光も音も俳優も同じラインで、そこから何かアイデアを出し合って作品を作るという形。実際台本も全部出来ないうちから、スタッフとああだこうだして、どういう空間にしようとか、皆でアイデアを出し合って作った最初の作品なので。それが一番うまくいった作品だなと思います。それまでは台本先行で作っていましたが、空間とか光と音に合わせて作ってみるという方法を取った。また、空間そのものとどういう風に関われるかということを、布を使って表現した。布一枚なんですね、セットが。その布がアパートの一室でもあり、海でもあり、砂漠でもあり、時にはスクリーンにもなり、壁にもなり、洗濯物にもなる。子供の頃に押し入れとか段ボールで遊んだ感覚と近い状態で作っている。その空間と関わりながら作っているので、そういうのを一緒に味わいに来て欲しい。あとは俳優を観て欲しいというのはありますね。ぼくは結構意地悪で、いくつもの物語を貼り付けていくというか、王様だけど引きこもりでとか、一人二役という意味でなくて、同じ人なのに違う役割を担っているようなことを俳優に要求したりするので、その中で俳優がどう必死に自分の物語を作っているかというのを観て欲しい。ある意味引き裂かれているんですけど。そういう状態でどういう風にいるのか。皆出ずっぱりなので、ほぼ。素の状態というか、そういう状態もある。どこから芝居が始まるのか。どこから先は素に戻るかの繋がりというか。
素に戻る瞬間もある。
■松井:でもそれはもう区別付かないですよね。素なのか、一体誰なのか。そのぬるっとした感じ。そこに居なきゃいけないので。普通ならぱっと切り替えて存在感を消すというやり方もあるんでしょうけど、そういう風じゃないので。晒されている。
俳優にいくつかの役割を貼り付けるという話でしたが、それをどのように演出されるのでしょうか。
■松井:例えば漂流教室で言うと、椅子にならないと怪物に食われるというエピソードがあって、皆椅子になろうとするんだけど椅子になれない。そして「俺は椅子になれない」と思った人から食われるんですけど、ぼく自身もそれは無理だと思っていた。でも誰かが自分の背中に座ったら、椅子のように持ち運んでそこに座ってくれたら、ぼくが思わなくても椅子になってるんです。ぼくもそのことで自分が椅子になる材料が揃ってくる。誰かが椅子として扱えば椅子になる。だから貼り付けていくのは他人であって、自分が思い込む必要はないのかもしれない。
風呂に入っているというか
演劇の面白さ、魅力をどこに感じていますか。
■松井:空間を共有していることだと思うんですけど。その場に居て、虚構を演じている訳ですけれども、でも実際に人がそこに居て、かと言って現実かというとどこか嘘を付いている。その嘘と本当が重ねられた状態を眺めている観客が居て、そしてそれは眺めているだけじゃなく、もしかしたら参加しているかもしれない。そういう嘘と本当のどっちでもいい状態を味わうことが出来る。風呂に入っているというか、居心地の良い空間というか、それを作れることが楽しい。居心地が良いだけじゃないと思うんですけどね。痛いと思うこともあると思うし、思い出したくもない記憶を蘇らせることもある。でもそれはたかが演劇でもあるし、でも切実なこともあるので、されど演劇ということもある。
ありがとうございました。
■松井:ありがとうございました。