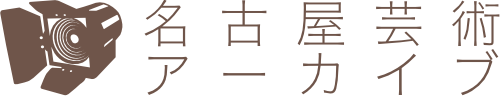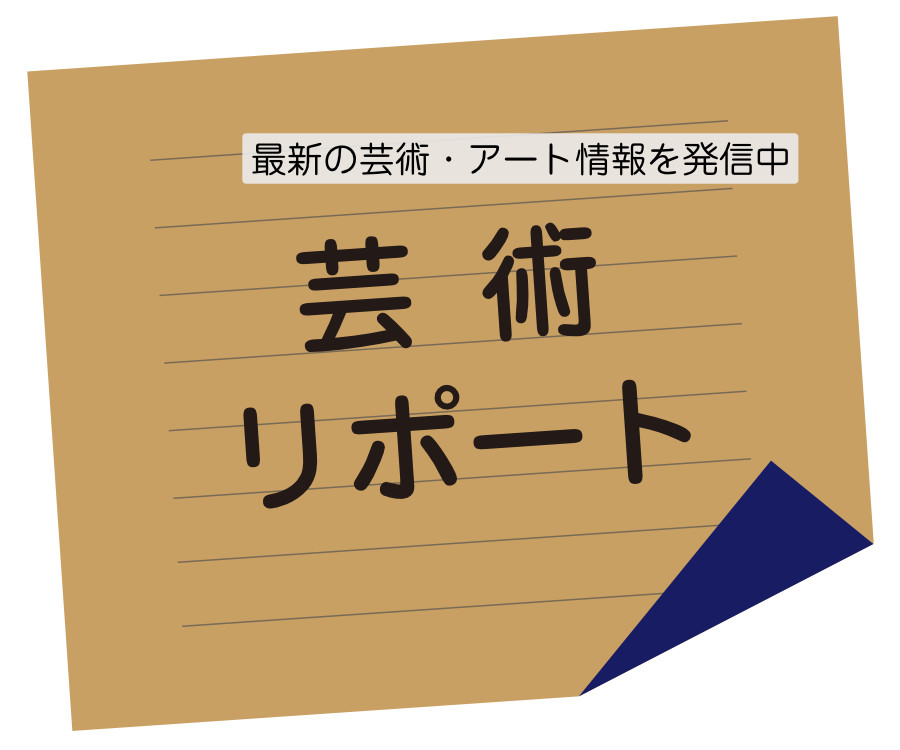世界が暗闇から明るく変わる瞬間
鈴江さんが演劇を始めた最初のきっかけを教えてください。
■鈴江俊郎さん(以下鈴江):高校の時に野球部だったんですけどね、男子校じゃないのに男子としか喋らない内気な少年だったので、大学生になったら文化的なことをして女子と喋らないといかんと。そして1982年当時、文化的なところということで映画サークルを見学に行ったんですけど、京都大学の映画部は哲学とか政治とかを議論する、おっかない雰囲気だったんですね。それはそれでいいんだけど、何か作りたかったし。それでたまたま看板が出てた劇団があったのでそこに入ったんです。それが『そとばこまち』で、関西の学生演劇ブームの中心的な存在の立派な劇団でした。なんなのか知りもしないで入ったら強烈に勢いがあって衝撃を受けました。でも適応できずにすぐ辞めた(笑)。また、そういうことと平行して対人恐怖症があったんですね。中学の時に苛められた経験があって、人が怖くなり、野球やってる時だけ自由になれた。ぼくは対人恐怖の中でも『表情恐怖』というものだったんです。自分の表情がどうなっているのかが怖いんですよ。人に不愉快な変な顔になっていないだろうとか、自意識過剰の更に行き過ぎた感じ。それが凄い苦痛で。このままでは20歳まで生きられないなと。それで治さねばと。死ぬならいっそ荒療治しようと。そのことがぼくの背中を押したんですね。でもそとばこまちで結局駄目だったでしょ。それで死ぬのかなと。ただ、そのことが「ぼくは演劇をやらないと死ぬぞ」というこだわりを生み出したんですね。舞台で表情や声色のコントロールが自分で完全に出来た時、演技できるようになった時、完全に治ったことになるんだ、って思い込んでました。そして3年生の時に自分で『劇団その1』を作り、治療が終わりました。劇的に治った。ぼくは自分の精神の病を治療する道具として演劇をやった、その成功例だと思います。むだな劣等感が解消した。こだわりが消えた。一気に日常が楽になって。劇的に世界が暗闇から明るく変わる瞬間だった。そういう喜びが演劇に結びついちゃって。演劇をやるということが、根本的な自己肯定が許される瞬間になるんです。ちょっと癖になりましたね。
最初は役者から入ったのでしょうか。
■鈴江:役者をしないといけない、治したいから。だけど怖くて、顔がひきつって、自分にとってもっとも恐れる最悪の状況が来るだろうと思ったから、まずはスタッフとして入ったんです。照明になったのかな。なのに、男の役者が少なかったから出演させられたんですよ。ガヤですけどね。でもガヤでも表情作らないといけないから。目立たないところで顔が引きつっていました。それが辛くて辞めたんですけど。また、劇団その1も役者をやるのが目的だったんですけど、怖かったので、俺が演出やるよって。座長演出だったらこんな顔しろとか言われないでしょ。そういう立場だったら出演できるかなって。そこから稽古だけの日々が半年続いて、第一回公演の時は他の奴が作演出をやって、ぼくが主演だったんですけど、その頃にはもう出演できるようになっていました。
顔見てたら分かるよ
そこから戯曲を書き始めたきっかけを教えてください。
■鈴江:芝居の達成感も味わって、どんどん自分の劇団で公演を重ねていたんですが、どうせなら脚本も書かねばならない、と思うようになってました。実はこっそり書いたりしてたんですけど、自分の書くものがつまらないので2〜3回挫折したりしていて。それも恥ずかしいから誰にも言わなかったりしてました。そして5年生になって、もう演劇をやめる時期がきたから、最後に何か残るものを作ろうって。どんなに駄目な台本でも最後まで書き切るって決めて。5年生の秋に黙って書き始め、何度も挫折しかけたけど、最後まで書き切って。それが最初の戯曲だったんです。でもその頃は劇団員との関係がむちゃくちゃ悪かったんですよ。演劇やってる人たちってアーティスト的な振る舞いが好きでしょ。無頼であるとか、酒飲みであるとか、いい加減じゃないと格好悪いみたいなものにぼくは馴染めなくてね。ちゃんとしようよってタイプだったので。でもそういう無頼な奴らには彼女が居て、ぼくにはいない(笑)。だから「拗ねてるんだ」って言われたり。だけど「最後の脚本書いたから読んでくれよ」って。皆を集めて読み合わせをしたんですけど、「字が汚いから読めない」と嫌な顔で言われる。じゃあその役はぼくがやる、その役はぼくがやるって、6人芝居のうちの4人くらいをぼくがやって。そういう読み合わせした時に、意地で、なんとか皆を感じさせたいと思って熱演したら、下を向いてる人たちが乗ってきて。皆を笑わせる為に書いてるし、皆がこんなの喜ぶだろうなと知ってて書いてるし、笑わせて急に泣かせてみたいなリズムの繰り返しみたいなの書いたら、皆笑っちゃって泣いちゃって、終わったら赤い顔している子がたくさんいたんですよ。終わった瞬間「やったね」って。これまで何度も台本書きましたけど、手ごたえはこの時のが最高のうちのひとつですね。結局口では褒めてくれなかったけど、顔見てたら分かるよって感じになっていたので。そしてそれで終わるつもりだったんですけど、「書いたから上演やってくれ」って運びになって、上演したら「書けるね」って感じになって。周りが期待し始めて。期待にこたえると周りが喜んでくれる。うれしいから次も書いて。大学時代で演劇は終わるつもりだったんだけど、そんなんでいつの間にか「書く人」扱いされて、その調子で続けて来てしまいましたって感じですね。
誰にでも許される権限じゃないと思う
影響を受けた作品や人物があれば教えてください。
■鈴江:ぼくは基本的な演劇の勉強をしていないし、漫画のほうが影響を受けています。ぼくが書き始めた頃は、『ガロ』って雑誌の作家たちが好きでした。つげ義春とか、蛭子能収とか、ひさうちみちおのように、緻密に構成してるんだけど破綻を狙っている、みたいな描き方。
自身で思う、自分の戯曲の特徴や癖があれば教えてください。
■鈴江:ぼくは舞台とか劇団が評価される前に戯曲賞を貰ったんですね。だからなんていうか、認知度が高まってきたのに、自分で書く作品を自分で上手に上演できない。そういうコンプレックスが強かったんですよ。だから、上演したらどうやったら面白くなるのか、というこだわりが強くなりました。演出の作戦込みの脚本を書いているつもりです。基本的に脚本は役者の為に当て書きするっていう意識で書いている。役者の呼吸とかリズムとか、なるべくそういうものを生かせるように書いています。
劇作家によっては一言一句間違えるなという方もいますが、鈴江さんはその辺のこだわりはありますか。
■鈴江:ケースバイケースです。役者が面白い奴だったら、役者が言いたいように言ったら面白くなるだろうし、役者が面白くない奴だったら、言いたいように言うと面白くなくなりますよね。誰にでも許される権限じゃないと思う。脚本が素晴らしかったら演出家は一言一句変えないほうがいいだろうし、演出に力があれば脚本はどんどん変えるべきだと思うし。基本的に脚本を人に渡したら、「脚本は元になるものにすぎないから、必然性があれば変えてください」って言ってますけどね。
一生に一度しか喋らないような言葉を
戯曲書く時のアイデアはどういう所から出てくるのでしょうか。
■鈴江:ぼくはね、座組の顔触れ。
当て書きですね。
■鈴江:そう。『劇団八時半』というのを長くやっていた時に、戯曲は戯曲賞を貰えるのに上演が面白くない、というのをなんとか克服したいと思ってやっているとね、役者が喋れる言葉を書かないと意味がないと感じるようになり、役者はどういうことを喋れるのかを模索するように一作一作書くようになったんですよ。でも自分としては失敗した台詞でも、役者次第で魅力的になることもあります。覚えているのは、「お母さんにかまって欲しい」という台詞。「お母さんは従業員たちのことばっかり心配していて、わたしのことを全然振り返ってくれない。だからわたしはずっと寂しかった」という台詞を。その時はテンション高く気持ち保って書いたんだけど、後で読んでみたらなんて幼稚な台詞なんだろうって。でも書き換えする時間もなく稽古場に持っていかなくちゃいけなくなって、役者にためしに演じさせたら、涙流して熱演してくれて、迫力があったんですよ。ああそうかって。こいつの話をよく聞いたら良かったって。こいつが喋りそうなことを書くっていうのをやればいいんだよねって。役者にはなにか表現したいことがあると思うんです、舞台に立つ上で。役者の中にあるんです、答えが。だからその役者と一所懸命喋ろうとしますね。その人たちが一生に一度しか喋らないような言葉をなんとか引きずり出そうとしてる感じ。役者が人として、ある葛藤をいくつもいくつも乗り越えたり、いくつもいくつも抱えていてくれれば、いくらでもこの人と書けるなと思うんですけどね。だから20人役者を使わなければいけなければ、その20人を眺めて、こいつらは何に見えるかなと。この人たちがいる場所ってなんだろうなと考えるところからスタートしています。昔は自分のことばかり書いてたんですけど、今は役者のことを書いています。勝手に役者のことを想像して書いてるだけですけど。
自分がやりたいことはわりと少数派なんだと
演出する上で最も重視することはなんでしょうか。
■鈴江:役者の魂が前面に出て炸裂するように、みたいなことを考えてますね。役者さんが出したことないようなエネルギーをなんとか出せるよう要求するようにしています。だから役者にとって不愉快な要求だったりすることもあります。苦痛を乗り越えた時に見た事のないようなエネルギーが出たりするので、それをなんとか出したいなといつも思っていますね。引き出しの中にあるものから手馴れた感じで処理されると退屈で面白くないので、自分のギリギリを見つめてもらいたい。そのギリギリを越える瞬間を共有したいっていう感じですね。
あえて役者の反発を生むような状況にすることもあるのでしょうか。
■鈴江:そんなことはないですけど。単純に一所懸命やれって要求をしますね。クレバーに器用にこなされる状況で送り出したくないという感じかなあ。だからいつも要求は単純にしようと考えています。昔、演出が下手だと考えていた頃は、役者に馬鹿にされそうだと勝手におびえちゃってて、高級ぶった生半可な知識で難しげなことを役者の前で演説してた。役者の稽古よりもぼくの語りのほうが長い稽古場でした。典型的なへたくそな演出ですよね。で、いま心掛けているのは、ぼくは出来るだけ喋らないようにしたい。当たり前ですけど、役者が実際に身体を動かす時間を長くしたい。それを「もっとくれ、もっとくれ」というようにしています。うまくできるかどうか、やっぱり難しいんですけど、それを目指しています。
一緒に活動するうえで相手に持っていて欲しい能力があれば教えてください。
■鈴江:『演技をする人』というのと、『演劇活動をする人』というのはちがうと思うんですよ。ぼくは演劇活動を丸ごと一緒にする気のある人であって欲しいですね。舞台の上で演技するというのは演劇活動のごく一部ですよね。会計を一緒に支え、チラシを一緒に撒き、舞台美術の木材をどこで買うとか、叩き場をどこにするとか、探したり頼んだり走ったり汗かいたり。そういうことを全部ひっくるめて演劇活動ですよね。それをやるのがぼくは好きなので。どこまで行っても全部自分でやりたいねって。それが楽しいって人と一緒にやりたいです。でもいまやそれは演劇やってる人の多数派ではないように感じます。だからぼくと一緒にやる人には、「2トンロングのトラック運転できますか」ってわざと挑発的に聞いたりします。トラックの運転って象徴的でね。必要になれば、やらざるをえなくなればなんでも覚えちゃおうって動いてしまう人が、劇団の中でもトラックを運転する人になる。そういう人はなんか必要だなと思えば、他の人がやらないようなことでも頑張っちゃうんです。エクセルとかワードとか、チラシを誰かに任せると金掛かるからフォトショップ覚えようとか。そういうことを二つ返事でやりましょうと言ってくれる人と、重い荷物を担ぎたい。だから荷物軽くして楽にスムーズに心地よくお芝居やって、華やかにお客さんの前に立ちたいというのはぼくとは少しずれるんです。でも全部の人がそうすべきだとは思っていませんよ。ぼくはそういうことが好きだというだけのことです。だけどそういうことを自覚するようになったのはようやくここ数年です。自覚してなかったから、自分の劇団ではよぶんな苦労をしていたのかもしれないです。でも、分かりました。自分がやりたいことはわりと少数派なんだと。だからこれを多くの人に押し付けちゃいかんと。最初から「無理だよね」「やりたいこと違うよね」と思ったほうがいいかもしれない、と割り切るようにしてます。僕はトラック運転したりたたきで材木切ったり打ったりするのを皆でやってる時間がまるごと好きだけど、演技したい人って必ずしもそんなことないんですよね。やっと最近気づきました。だから仲良く一緒にやれるように、最初に用心深く聞きますね。「トラックの運転できる?」って。
一緒に呼吸できるくらいのパフォーマンス
最後に演劇の面白さ、魅力をどのようなところに感じますか。
■鈴江:演劇って観る人とやる人とでは面白さが違うと思うんですよね。演劇をやるほうが観るより数倍面白いと思うんですよね。役者をやっていれば興奮できるし、客観的に見たらくだらない芝居でも、やってる人は感動してますもんね。お芝居は観るもんじゃなくやるもんだなって。やることが面白いのは、緊張があって、不安があって、恐怖があって、それが本番になったら恐怖していようがなんだろうが舞台に立たないといけない。舞台に立ったらなんかやり切った感じがする。その達成感が堪らなく気持ちいいので。また、演劇は手間ひま掛かるのでね。それだけ手間ひまかかるから面白いんだろうなという気がします。演劇を観る側としては、面白い演劇って滅多にないと思うんですよ、残念ながら。ライブで面白いっていうものは、やっぱりお客さんと一緒に呼吸できるくらいのパフォーマンスじゃないと駄目ですよね。呼吸が合うってことだと思うんですよね。お客さんと役者の呼吸が一緒になる。お客さんは良い芝居に集中しちゃうと、役者が息をしたら息を吸うし、息を止めたら息を止めるし、それは映像を一人で観てるのとは全く違う。空間が一体となるから面白いのであって、演劇はこういうのが実現出来るので、それが魅力ですよね。
本日はありがとうございました。
■鈴江:いえいえいえ。こんな感じで良かったですか(笑)。