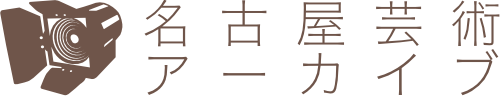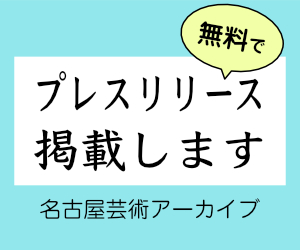演劇をやっていくというのはこういうことなのかなあ
柳沼さんが演劇を始めたきっかけを教えてください。
■柳沼昭徳さん(以下柳沼):鈴江俊郎さんの影響が大きいですね。最初は高校演劇です。うちの顧問が社会人劇団をやっていたのですが、「最近鈴江俊郎という凄い劇作家が京都に現れた」と。そして出て来たのが鈴江さんの『区切られた四角い直球』という尖った作品なんです。いやまあ、高校生がやるには難解な作品なんですよね。でも高校生が主役で、大人がやっても成立しにくいということでぼくらが初演だったんです。で、それを鈴江さんが観に来られて、「ぼくはあんなつもりで書いたんじゃない」と辛辣なこと言われて(笑)。それで凄い人がいるなと。高校演劇っていうジャンルしか知らなかったので、実際にどんな人がお芝居やっているかというのを目の当たりにしてもの凄い衝撃だったんですよ。それから高校卒業後、受験の失敗などがあって、本当に自分のやりたいことがなんなのかと考え、近畿大学の演劇芸能専攻に入りました。そして3年の時に鈴江さんが専任講師として来られたんですよ。そこでは1年後に発表会をするという授業だったんです。これまではブレヒトがどうのこうのとか、講師は遠い存在として、色々教えてもらうという感じだったんですけど、鈴江さんは、「いいか、まず稽古場は綺麗にせなあかん。皆でここを今から掃除する」と(笑)。環境を自分たちで整えるというところから、公演に至るまで、小劇場に関することを一通り撫でることが出来ました。それでそれが終わった時に感動して泣いてしまったんですね。卒業公演でもないのに凄いテンション高くなって。そこで鈴江さんが「劇団作れ。やりたいメンバーと社会に出て行くべきだ」とおっしゃって。ぼくは就職するつもりだったんですけど、そういうのもありかなと思って劇団を始めたんです。

烏丸ストロークロック「八月、鳩は還るか」
撮影:東直子
その時のメンバーは同じ大学の方。
■柳沼:同期なんです。かたや、同期には『デス電所』。人気者の人たちが。ぼくも友達ではあったんですけど、ぼくは違うことがやりたいなって思って。それで烏丸ストロークロックを立ち上げたんですけど、3人しか集まらなかったんです。非常にこう、先行き不安なトリオが(笑)。そこではぼくも俳優をやろうと思ってたんですけど、鈴江さんに、「台本書く人がいないから劇団できないですよね」って話をしたら、「アホか。お前書いたらええやん」って。ぼくがジャンケンで負けたっていうのもあるし、煽られたっていうのもあるし、書いてみて。で、文字通り地味な公演になったんです。初回が7人だったんです、客が。3回公演で10人、15人みたいな。まあ酷い公演でした。それっきりでやめようかと思ったんですけど、鈴江さんが観に来てくれて、凄い面白かったと。興行的には大火傷でしたけど、お客さんが来たからイコール良い芝居ではないんだな、と。そういう面も見えた。なら自分たちのやりたいことを続けていけばいいじゃないかと。近大は大阪にあって、仲間もいるので、最初は大阪で公演やっていたんですけど、徐々に京都に。ちょうどその頃は『京都芸術センター』という、ちゃんと申請さえすれば無料で使える贅沢な施設が出来ようとしてたのもあって。アトリエ劇研の杉山準さんであるとか、鈴江さんであるとか、当時若手でトップクラスの方々が実際に環境の整備というところも自分らの手でやろうとしていた。それらを見て、演劇をやっていくというのはこういうことなのかなあと。それ以来、愛着もあるので、京都でやらしてもらっている訳ですけれども。ちょうどぼくが始めた頃に、活躍されている方がいらっしゃるというのは非常に希望が持てた。京都という土壌で芝居を続けていこうというのはおのずと出来上がっていった。
劇団名の由来を教えてください。
■柳沼:地味なメンバーではあったんですけど、京都にはセンターロード、烏丸通りというのがあって。京都の中心というね。厳密に言うとちょっと曲がってるんですけど。あんまり大きな声で言うと恥ずかしいので、京都では言えないです(笑)。
ストロークロックのほうの由来は。
■柳沼:音韻で決めました。語感で。ギターのストロークってあるじゃないですか。それだけで俺たちはやるぞっていうのも後付けであります(笑)。
流通し得ないもの

作品のアイデアはどのように浮かびますか。
■柳沼:作品によってまちまちで、それも変化していってるんですけど、今は一番何に興味があるかって言うと、演劇の特性は空間だと思うんです。その空間というのは、流通し得ないものとしてそこにあって、ビデオを撮ったとしても再現できない。それが演劇の生き残る道だと思うんです。そしてその空間を何で構成するかというと、人だと思うんです。人が居て、関係性があって、事が起こって、空間の温度が増し、濃度が高まり、いつの間にか黒い空間に粒子が見えるくらいの密度を高めることができる。そこの人の可能性というかね、関係性、というのを追求していきたいなと思います。だから、作品の想起のアイデアの元になるものというのは、分かりやすく言うと、男と女。恋人とか夫婦とか友達とか。そこから始まって、登場人物たちと社会と結びつける為になにか実際にある社会的な設定。コミュニティだとか、社会システム。会社だとか。皆が誰しも思ってはいるんだけど、ちょっとずれた所にあるコミュニティだったりとかを扱うようにしたいなと思っていますね。そこから作品が生まれていきます。
演出するうえで特に気をつけていることがあれば教えてください。
■柳沼:これはさっきの話と繋がるんですが、生の感覚。一番最重要事項だと思ってるんです。例えば、役者がね、なんらかの実感を持って喋るとか、何かを込めて台詞を言うというのは非常に不自然だとぼくは思うんです。人って喋っている時に感情とか意識してないですよね。そういう不自然な部分を排除して、関係性を重視するようにしています。具体的に言うと、台詞を間断なく叩き込む。応酬をする中で役者がふっと、なにかこう自分の実感を越えたところで無意識の部分で生まれる恐怖感だとか雰囲気が起こるように仕向けていく。
外の環境から作っていく。
■柳沼:そうですね。感情が追いつかない状況まで役者を追い込んでいく。そういうことはどこの現場でもやることですね。いまも『異邦人』でやっています。そうしてくると、本人が思っている以上の魅力が現れてくるから。不安定ではあるんですけどね。出来る時も出来ない時もある。でもそれをできるだけ確率を高い方に持って行く。というのが、ぼくがやっていきたい所ですね。何か型に嵌めるんではなくて、そういう環境を作る。
考えてみようぜ
その不安定を高い確率にどうやって持っていくのでしょうか。
■柳沼:そういう稽古をする反面、逆に話すということ。裏付けをしっかりしておく。それを最初に入念にやっておくと、中々ズレが生じない。なんで自分がここにいるのかという動機付けがあると。なにかおかしいなと思っても修正できる。一番理想的なのは、俳優がもっとクリエイティブになるべきだと思うんです。どうしても演出家、作家の力がバランス的に強くなる。そうじゃなくて、役者が考えて、創造的なところに踏み込んでいくとそうはなかなかならない。お人形さんじゃなくなる。常に自分で考える。自分たちが舞台上でなんとかする力を付けていく。メンバーの中の信頼性を高める。それを丁寧にやることで、ブレが少なくなる。例えば、京都でアトリエ劇研が主催する『劇研アクターズラボ』というアマチュアからプロを目指す人のための俳優養成セミナーがあって、そこでワークショップの講師をしているのですが、その中でも俳優自身が自分の置かれている状況、どこで生まれて、どういう問題を抱えているのかを自分で考えてくださいと。その裏付けを自分で。別人格を考えてもらって自己紹介してもらう。それを聞いて当て書きすることで、俳優としての役作りの手間を省けるわ、俳優も頑張らなくてもいいわ、技術そんなにいらないわ、お芝居の説得力が出るわ。役者自身も自分のことを考える、関係性を考える。そうすることで根の演技が出来る。
京都っていうのは、作家が強い土壌でもあるんですね。役者はバイトしていかないといけないので疲弊して辞めてしまう。そういう構図をどうにかしたいなと思って、ちょっと役者、考えてみようぜ、と。自分たちで台本書けるじゃない、という感覚ですよね。ぼく自身が近畿大学で最初の頃やっていた授業は、2年くらい台本無しで、即興演劇を毎週2時間くらいやる。それを繰り返していたので、台本を書くぞという時にあまり抵抗が無かった。
即興で演技するように台本を書くことが出来た。
■柳沼:そうです。俳優がもっとクリエイティブで楽しく感じることが出来れば、もっとお芝居に興味が持てるようになる。ぼくも30を越えたあたりで、自分の脳の中にあることを再現することに、そんな人生経験がないものですから、面白くなくなったんですね。なにか人と出会う、俳優と出会うことで力を増すことが出来れば、ぼくが予期しなかった豊かな作品が作れるんじゃないかなと思っています。
茶番度をどうやって薄めていくか
烏丸ではエチュードをよくやるのでしょうか。
■柳沼:エチュードというか、その前段階ですね。話を聞く。前回公演『仇野の露』出てくれた年配の方は、ベテランのように思われるかもしれませんけど、劇研アクターズラボから始めた方です。あの方はそういう作り方でやったんですね。奥さんがいらっしゃって、凄い健康なんですけど、周りではボケたとかそういう話があるので、自分がこうなったらどうするんだとか考えて。やはり70の役者さんって覚えるの難しいんですよ。だから自分で喋ってもらう。箇条書きで。NGワードを決めて。
台本はあるにはあったんでしょうか。
■柳沼:あるんですけど、最終的にはポイントだけを押さえて喋ってもらいました。あれは夫婦の二人芝居だったんですけど、俳優同士が仲良くなるところから始めて、「わしはこう考えてるんだけど、お前はどうだ」と。そして仮想の夫婦が出来上がる。あとはぼくが調整していくだけ。話し言葉と演劇は違うじゃないですか。そこの整理はします。『えー』『あの』『その』とかの雑音は排除していく。
そこのバランスは柳沼さんが取っていく。
■柳沼:そうですね。それと、演劇の構造的なところで、フィクション性だけではお客様が入りにくいなというところはある。メタ構造で観る芝居は多い。そこは皆考えるところだと思う。茶番度をどうやって薄めていくか。茶番にならない。更にその茶番を茶番であると恥じらいを持ってやるんではなく、どうやったらお客さんを巻き込めるか。それで、そうしようと思うと振付けだけじゃ無理なんですよね。この人である必然性、この人でないと出来ないものを考えないと。今回はプロデュース公演ということで、こういうメンバーなら間違いないよね、というのはあるんですけど、それよりも、この空間にいて不自然じゃない人というところで決めました。
集団というものは不思議だな
一緒に芝居をするうえで、相手に持っていて欲しい能力はありますか。
■柳沼:皆が一部である、不完全であるということが前提としてありますね。だからお互い甘えるんじゃなくて、委ね合う。委ね合う為には相手を信じないといけない。自分もそれに応えないといけない。これをコミュニケーション能力というのか分からないですけど。それくらいですね。自分自身が俳優だからこうとか、照明だからこう、ということではなく、それぞれがひとつの空間に奉仕する。そういう感覚を共有できる人ですよね。そういう方と一緒にやってたい。
演劇をやっていて、楽しいとか、嬉しくなる瞬間があれば教えてください。
■柳沼:稽古中はそんなこと言ってる場合じゃないですけど、幕が開いて、さっき言ったような作り方をしていると、予期せぬ方向に行く。10人居たとしたら、10人以上の力になっていく。メンバーでしか生まれないものが出来る。その現象というか、自分自身でも予期せぬことが起こる集団の力。えも言われぬ興奮を覚えますね。舞台で、台詞にはないんだけど、ぽっと言うようなことにもの凄い痺れたりするんですよ。10回公演とかやってると飽きてくるじゃないですか。ぼくはもう観るしかないので。だからもっと面白いことしてくれよって言った時に、それお前がやりたかっただけやんというのではなく、そのメンバーで、その空間で、そのお芝居の中で、生まれてくるもの。集団というものは不思議だな、なんて可能性があるんだろうと思う。
演劇は割り切るべきだと思うんです
烏丸ストロークロックの見所を教えてください。
■柳沼:これどうやって作ってるんやろうなって思われると一番小気味良いですね(笑)。どうやったらこんな風にできるんだろう。もの凄いオーソドックスなことをやってはいるんだけど、そこを凌駕している。普通にやっていたらこうは作れないだろうなという、不思議な感覚というのは、いま喋ったように作られているからなんですけど、そういうやり方で生まれるからこそ繊細なんだというのはあるんですよね。ちょっとした人の動きによってガラっと印象が変わってしまう。そういう繊細な部分を観て頂けると嬉しいですね。あとは、京都のお芝居というのは、アングラかエンタメか、二極なんですよね。極端に言えば。でもね、その真ん中もいるよ、ストレートにやってる人もいるんだよという。それがこう使い古されたものではなく、そこで新しいことをしようとしている。それは手法が新しい方法という訳ではなく、関係性を新しくしようとしている。
これは役者の地力がもの凄く必要ですね。
■柳沼:しんどいと思いますよ、役者さんは。
演出としても、役者の能力を引き上げていかないといけないですね。
■柳沼:そうですね。引き上げるというか、もっと良く見えるのにという客観的な視点で喋っているから、「それ成立してない」とかばっかり言ってますね。「これはバランス悪いね」とか、「これは自然界に存在しないね」とかやってます。

他に言い足りなかったことはありますか。
■柳沼:会話劇にこだわってます(笑)。あと、東京に興味が無いというところですね。なにか消費される感覚に耐えられない。ぼくは消費対象になったことはないんですけれども。ぼくはこの空間を流通させるべきではないと思っていて。むやみやたらに。確かにたくさんの人に観て欲しいし、それでブレイクしていければ嬉しいことなんですけれども。それよりもぼくはこんな情報たっぷりの世の中ですから、むしろ情報のほうが多い世の中ですから、そこを大事にしたいし、演劇は割り切るべきだと思うんです。情報ではない、我々のやっていることは。ぼくらもお客さんの顔を認識できるくらいの綿密な関係性を築いていきたいな。来年からは久し振りに京都以外での公演を再開しようと思っていて、それが三重、岡山、舞鶴。そういうところでやらしてもらうんですけど、「こういう作品観てください」「観ました」「はいそれでは」というのはもう嫌なんですよね。そこにぼくたちが行くことで創造的な動きが起こる。具体的に言うと一緒に作品作るだとか。交流したいなと思います。
本日はありがとうございました。
■柳沼:ありがとうございました。