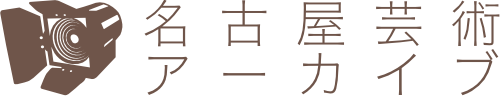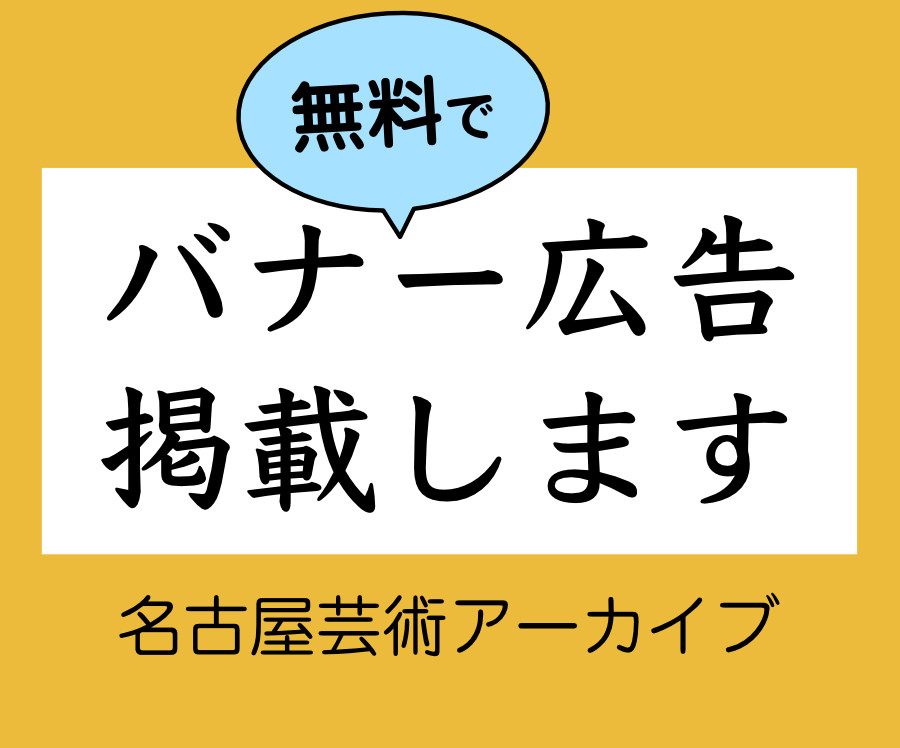色々なことをやりたいなというタイプみたいですね
初めにこの世界に関わったきっかけを教えてください。
■唐津絵理さん(以下唐津):両親に聞いた一番最初の機会というのは、幼稚園の時にお誕生日会がありまして、そこで「ダンス踊りたい」と言って、即興で皆の前で踊ったというものです。たぶん3歳か4歳の時。身体を動かすことが好きで、5歳の時に近所のダンススタジオを窓から覗いていたら先生がおいでって言って。
どのようなダンスのスタジオだったのでしょうか。
■唐津:モダンダンスですね。たぶん児童舞踊に近いかな。石井漠の義理の妹、石井小浪さんが始めた日本特有の舞踊で、子供達の教育の為にダンスを取り入れるという。
そこからどのくらい続けられたのでしょうか。
■唐津:そこから10歳まで。それから父の転勤で熊本に行くことになったのですが、創作に重きを置いたダンス教室はなかったんです。唯一バレエ教室があったのでそこに入りました。なにかひとつの習い事に打ち込んだというよりも、両親が器械体操の選手だったので、そういった現場に小さい時から行って器械体操のレッスン受けたり、また父がフィギュアスケートの指導員だったもので、スケートをしたり。でも結局なにか身体で表現するようなものが好きでした。
器械体操やフィギュアスケートで両親のようになろうと思ったことはありますか。
■唐津:なかったんですね。たくさんの運動を経験させてもらいましたけど、それを深めていくということにあまり興味がなかった。熊本で入った小学校、中学校では演劇部に入っていました。興味があるのは全て舞台や身体表現に関わることでしたね。ひとつのことを極めることができないというのが欠点なんですけど。色々なことをやりたいなというタイプみたいですね。ある程度やるとそれと関連した別のことに興味がでてくる。高校では新体操がやりたくて、新体操部のある熊本高校に行きました。そして大学に入ろうという時に、ダンスとかやってる人は皆そうだと思うのですが、これがどう将来に繋がっていくのかと、はたと困ったんですね。それで行けそうなところを探していたんですけど、たまたまお茶の水女子大学の舞踊教育学科というところを見つけたんですね。
そこから現在に至るまでを教えてください。
■唐津:お茶の水女子大学では実技中心ではなく、学問的に学ぶということをしていたので、舞踊論や舞踊美学などの授業受けながら外で活動していまして。そうやって大学4年間は過ごし、それで大学院まで行きまして。もう少し勉強したいかなって。そこで、舞台上でダンスだけをやっていることに疑問が出てきて、自分が表現することでどれだけ社会に貢献できるのか、とか考えるようになって、突然自分がダンスをすることに対する興味が薄れてきてしまったんですね。ちょうどその頃ニューヨークのダンスフェスティバルにダンサーとして出させていただく機会があって、音楽とダンスのコラボレーションによる作品の1週間くらいの公演で、その時の経験が凄く大きかったんですけど、どの公演も満席で、たまたま通りすがりの方が観に来てくれたり、その舞台環境にカルチャーショックを受けたんですね。こういう環境を作ることに対して興味が湧いてきた。その時すぐにアート・マネジメントを意識した訳ではないんですけど、ちょっと視野が広がってきて、舞台を一般的に広めていくことのできる仕事について調べ始めたのが大学院の時ですね。
そこから愛知県芸術文化センターに繋がるのでしょうか。
■唐津:そうです。放送業界とか色々なメディアとか調べ始めて、たくさんの人に舞台芸術の存在を伝えるにはどうしたらよいかと考えていた時に、芸術文化センターのほうからお誘いをいただきました。 パフォーミング・アーツ専門の学芸員を採用したい、って。最初に担当したのが舞踏の『山海塾』でした。
ああいう風になれないならやりたくない
これまで観たきた中で最も印象に残った作品を教えてください。
■唐津:人生を最も大きく変えたのは、木佐貫邦子さんです。大学上京してすぐ、彼女の『てふてふ5』というダンスを観て。東大の放送研究会というサークルに入っていたので、ステージショーの司会として東大の学園祭に参加したんですが、彼女はこの学園祭に呼ばれて来ていたんですね。なにか表現することができないくらい衝撃を受けた。木佐貫さんの作品を観たということが、もしかしたらいま自分がダンスの舞台に立つことが出来なくなった大きな要因かもしれない。
勝てないと思った。
■唐津:勝てないというか、ああいう風になれないならやりたくない。
■鳥羽あゆみさん:なにが伝わってきたんですか。
■唐津:すごい衝撃でした。美しいダンスというものはたくさんあるけれども、この『てふてふ』というダンスは2/3が動かない。『てふてふ』って、蝶々って意味なんだけれども、最初はどう見てもいわゆる通常のイメージでの蝶々には見えない。動かないでいるのは、幼虫かな、さなぎかな、なんて考えてみたり。それが本当に最後の短い時間に羽ばたいていくという踊りで、これまで観たことのない世界観、身体の無限の広がりを感じました。
2/3が動かないのに、その間を保たせることができるというのは凄いですね。
■唐津:一緒に観に行った友達は「わたしはちょっと駄目だった」という人ばかりだった。でもわたしは言葉も出なかった。蝶ってひらひらと美しいイメージがあるけど、それは蝶のほんの一瞬でしかない、じっと耐えている時間の方が長く、それこそが実は大切なんじゃないかって。物事の本質を身体で表現してきた。これまでの自分の思い込みに気がついて、価値観が覆されたこともショックだったのだと思う。あとはですね、ちょうど今回のあいちトリエンナーレで上演するダンスカンパニー・ローザスの『ローザス・ダンス・ローザス』という作品も私にとって重要な作品です。この仕事を始めて2年目に、職場研修で東急文化村のシアターコクーンに制作のアシスタントで行ったのですが、その時にこの作品をやっていました。そして凄いラッキーなことに、舞台が日々進化していく様子が観れた。しかも「コンテンポラリー・ダンス」という言葉がようやく日本で出て来て、当時は、そういうダンスをやっても客席ガラガラという状況だったのですが、それが口コミで人がどんどん増えて、最後は行列が出来た。そういう日本に新しいダンスが芽吹く瞬間に立ち会うことが出来た。
たぶん正解はないと思うんです
トリエンナーレでは『キュレーター』という肩書きを持っていますが、キュレーターという仕事はどういうものなのか教えてください。
■唐津:パフォーミング・アーツの世界でキュレーターという言葉はあまり使わないんですね。今回はトリエンナーレ自体が美術の文脈での芸術祭なので、名称もそれに合わせているところもあります。わたしもなにをすべきなのかは、日々自問自答しています。そもそも芸術文化センターに入る時から「学芸員」という肩書きなので、まずそれで来てくださいというオファーがあった時から、すでに自問自答が始まっています。同じような立場の人間は、通常の劇場では、プロデューサーとかディレクターと呼ばれていると思いますし、今でこそ、多くの劇場に「制作」といった職種がありますけれど、当時は公立文化施設においてそのようなものはほとんど無かった。文化センターが18年前に出来ましたので、パフォーミング・アーツの世界で「学芸員」という職を作った多分最初の組織なのではないでしょうか。今もほとんどないんですねどね。そこでまずは美術館の学芸員の役割というところから考えた。資料の調査とか研究、情報集め。それを元にした企画。またそれについて丁寧な解説を加えたりするという美術の学芸員のフォーマットみたいなものがありましたので、それを舞台芸術に置き換えた場合になにが出来るのかなって、考え始めた。なのでたぶん正解はないと思うんです。
唐津さん自身もそれを模索している途上なのですね。
■唐津:そうですね。海外の状況をみたりする中で、これまでこの肩書きに違和感を持っていたりしたんですけど、似たような職種の人たちも出て来ているので、ようやく、自分なりの「キュレーター」としての仕事の役割がしっくりしはじめたところです。わたし自身が文化センターでやろうとしていることは、大きくふたつあると思うんですけれども、ひとつは様々な状況を伝えていくこと。世界最先端で起こっているリアルな今の舞台芸術の状況を、様々な切り口でみせていくこと。これは美術では企画展に近いと思います。あともうひとつ舞台芸術に学芸員が果たせる役割として、プロデュース作品を製作していくこと。これは創作する場を作ること、愛知という地域に創造環境を作っていくこととも繋がっています。日本の場合芸術環境が恵まれていないので、なんでもやらないといけない。学芸員は『雑芸員』と呼ばれるくらいなので。でもその中でその人がいなかったら成立しない作品を示したいなと思います。例えばどういう人とやったらどんな作品が生まれるだろうとか、あとはどんなテーマや題材、配役が相応しいか、とか。特にダンスの世界は振付家一人の人に与えられる役割が大き過ぎる。かと言って彼らがきちんとした演出法や舞台についての知識や技術等を学ぶ場所がない。知らないまま手探りでやっている。今までの経験からその手助けすることも重要なのかなと感じています。最近では日本でも「ドラマトゥルク」という言葉が使われるようになってきましたが、文化情報センター内にはアートライブラリーもあって、作品の文献調査等もすぐにできますので、過去の文学作品であれば、作品成立の背景を調べたりとか、作品自体を強くして行く為のアドバイスをしたりだとか。<ダンスオペラ>というプロデュース公演の企画の中では、そんな役割で創作に取り組んでいることが多いですね。一人の持っている能力の限界はあるので。そういった仕事も学芸員の仕事のひとつかなと思っています。
出会いの仕掛けは必要かなと思います
トリエンナーレではどのような形で関わっていくのでしょうか。
■唐津:今回に関しては、芸術監督の建畠さんが美術の方で、どちらかというとこれまで芸術文化センターの自主事業とは違うアプローチでやっていきたいということでしたので、監督とお話しながら、美術中心のトリエンナーレの中から、より複合的な視点で舞台芸術にアプローチしています。特にトリエンナーレのテーマになっていることが3つ「先端性」「複合性」「祝祭性」ですね。3年くらい前から色々な作品を視察して、情報を集めて、今回のテーマに合ったアーティストや作品を探して、トリエンナーレで上演してもらうために交渉。それがひとつの大きな仕事ですね。あとは今まさにやっていることですが、コンセプトを丁寧に説明していくことですね。トリエンナーレではたくさんの作品がありますよね。劇場でやるものもあれば、屋外でやるものもある。美術のギャラリーでやるものもあります。そのような作品をひとつだけ観ると、単なるアーティスト個人の作品、ということになるんですけれども、いくつか観ることによってそれぞれの人にとってのオリジナルのトリエンナーレができると思うんですよ。その繋ぎ方。もちろん自分の興味で観ていただくのが一番いいんですけれども、分からない人もいると思いますので、広報を通じて、これとこれとこれを観るともっと面白いというような手掛かりを考えていきたいなと思っています。 今回特にお薦めしたいのは、ローザスがデビュー当時の作品と合わせて、トリエンナーレのファイナルに上演する『ドライ・アップシート(3つの別れ)』。マーラの『大地の歌』をベースに、ローザスのアンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルが、フランスの振付家ジェローム・ベルと共同制作した複合的な作品です。舞台上にダンサー、演奏者、オペラ歌手がのって、動いたり、話もするという驚きの舞台。これだけの世界的な振付家になっても、さらに未知の世界へ挑戦し続けていることも驚きですが、この作品がオペラの殿堂であるモネ劇場で初演された作品だということも日本との芸術環境の違いを感じますね。
最初の話にあったような、ふらりと来られるような劇場となるような取り組みはなにかされていますか。
■唐津:芸術文化センターはハードの性質上、ふらっと来られる劇場ではない、と言われることが多いので、劇場と劇場以外の無料空間やまちのなかを繋ぐような企画も考えています。例えば、ある週末の1日には、小劇場での公演と、ギャラリーGでのパフォーマンス、そして「まちなかイベント」の3つくらいの公演を続けて観られるようにプログラムを組み立てています。そして、その後に、それぞれのアーティストの生の声を聞けるトークカフェを開催する、といった仕掛けをプラスすることによって、観客ともアーティストとも芸術祭ならではのコミュニケーションが生まれるといいなと。
カテゴリーを分ける必要はないと思います
日本の舞台芸術の特徴はなにかありますか。
■唐津:ダンスも演劇も教育システムがない。美術や音楽に比べると、専門的な大学もないし、専門的な劇場もない。言い出すと、ないものだらけなんですけど、これは色んな方から言われ続けていることですね。あとは、ジャンル毎に閉じていると思います。今回トリエンナーレでは複合性というものを挙げていますけど、それはジャンルを越えるということ。例えばヤン・ファーブルは美術作家でもあるし、表現をするには舞台のほうが適切だと思えば、演劇作品もオペラ作品も創作しているし、ジャンルにこだわらず表現するものに応じて手段を変えていく。常に最先端をいくアーティストにとっては、それが自然だと感じています。日本の場合はまず、ジャンルありきで、作品を創造するというよりも、まず「ダンスをしたいのよ」、というところから始まるので、そこから出ようとしない。
職人気質なのでしょうか。
■唐津:学校教育に原因の一端があるのだと思っています。創造環境がないということ。それはアートに限らないことだと思いますが、管理社会の中で育てられてしまうので、自分がいる場所から出るということを良しとしない。人と違うことを認めてくれるのがアートだと思うんですけれども、学校は人と違うことを許さない場所になっている。そうやって育てられた子供が大人になって、自分と異なる世界に居る他者を認めるのは難しい。そもそもカテゴリーを分ける必要はないと思います。日本人って、「あなたはA型なのB型なの」みたいなふうに何でも分けたがる。アートとは違うところでもそういうことがある。仲間を作りたがって、そこに入らない人は「変人」みたいに言われたり。あと、自戒も籠めて言うんですけど、教養ですね。海外だとアートに関わる人は自分のジャンルだけではなくて、他ジャンルのことにも詳しいし、社会への関心も高い。ダンスに関しては技術を極めようという方が多いので、他ジャンルへの関心が薄い。アーティストとして活動する以上、自分の活動がどのように社会と繋がっているかを考えられないといけないと思いますね、社会に色々な意味で接点持てるようにしないと。一方的に自分のやりたいことを押し付けているようでは社会からも受け入れられないと思う。最近の例だと、アンヌ・テレサやジェローム・ベルは、日常的に環境問題に真剣に取り組んでいて、今回来日するのにも、最もエネルギー消費量の少ない方法を調べて来るとかね。一般的に日本のアーティストは社会的な意識が希薄だと感じています。
自分が変えたいと思ってますね
唐津さんの仕事で最も必要な能力はなんだと思いますか。
■唐津:常に物事を俯瞰的に、客観的に見ることだと思います。そういう意味でのバランス感覚。でも必要な時には思い切れる大胆さ。作品創りのような所には緻密さを要求されますけれど、思い切ったこともできないと、新しいものは生まれないと思いますね。
これまでこの仕事を続けてこられた原動力はなんでしょうか。
■唐津:この仕事をする人間が少ないですよね。なので、この仕事の重要性を世の中に知らさなきゃいけないという使命感というか、自分がやらなきゃ、っていう思い込みですね。これまでの関係だと、どうしてもアーティストとそれをサポートする人という上下関係があるように見える。でも、協同パートナーだとわたしは思うんですね。更にそこに観てもらう人との三角形ができると思うんですけど、これから日本における舞台環境を作っていく為に一番重要な役割になるのではないかと思っています。昨年まで文化庁の文化政策部会の中で『アートマネジメント人材等の育成及び活用について』というテーマで、私も委員として3年間議論を重ねてきているんですけれども、国もアート・マネージャーが育たないと日本の舞台芸術界が発展しないと認めている訳です。それでも食べていけなかったりポストがなかったりしてなかなか増えないし、どちらかというと裏の仕事、あまり報われないというイメージがありますよね。確かに今はそういう部分が大きいんですけど、そうではないように変えていかないといけない。いじけてても出来るものではないから、それならば、自分が変えたいと思ってますね。もちろん、同じ志を持った人たちと一緒にですけど。だから、最近は、特定の仕事に自分自身を縛り付けてはいけないと思うようになった。それこそ、固定のジャンルにカテゴライズされることと同じですからね。ベースをもちながらも、柔軟な発想で地域を越えて、日本レベルで、舞台環境を高めるために私ができることはしていきたい。こういう仕事をしてると結婚ができないとか子供ができないとか、特に女性にはハンディがあると思うんですよ。夜も遅いし。制作者の方には結婚していない方、子供のおられない方が多いですよね。でも実は一般の人たちに届けたいのであれば、一番近い人たち、家族も含めて近くにいる人に伝えていくことができなくては。自分も舞台業界、といったような、一般の人から隔離されたところからアートに関わるのではなくて、日常での感覚を大切にしながら、いつかその人たちに舞台を届けて共有したい、と思っているんです。今はまだ存在を知らなくても、アートに出会うことで救われる人が確かに存在すると思っている。ヤン・ファーブルも「自分はアーティストになっていなければ、犯罪者になっていた」って言ってましたけど、現代のような管理社会にとって、そこは紙一重のところがあると思うんです。私にとっては、木佐貫さんの舞台との出会いが新しい自分との出会いとなりましたし。だから本当に必要としている人たちのもとに舞台を届けられたらいいな、と思っています。
本日はお忙しいなか本当にありがとうございました。
■唐津:ありがとうございました。