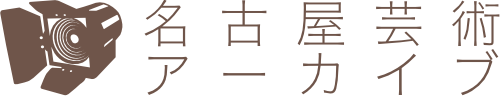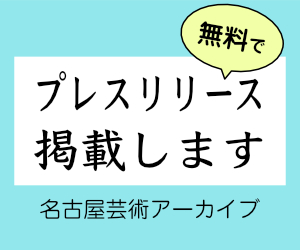武田久美子のキャンパスリップ
まずは映画に関わったきっかけを教えてください。
■柿沼岳志さん(以下柿沼):高校の時くらいだと思いますが、誰にでもあると思いますけど、芸術だとか文学に関心を持ちますよね。ぼくの場合はそこから始まったんです。子供の頃から映画ファンだったという形では全然ないんです。そういうものに対する関心から始まって、で、日大の芸術学部に入学したんですね。ぼくは最初演劇を専攻していて、その後映画に移ったんです。
どういう経緯で演劇から映画に移ろうと思われたのでしょうか。
■柿沼:東京に出てきたので、芝居、映画と、アクセスが増えるじゃないですか。山のように色々なものを観ているうちに、自然と映画に惹かれていったということでしょうか。卒業後はテレビの制作会社に就職しましたが、やはりいつか映画をやりたいという気持ちはずっと持っていました。そんな時に、渡部先生が監督された映画(「ライフ・イン・モーション Life in motion」)にスタッフとして呼んでいただいたのが縁で名古屋学芸大学に勤務する事になったのです。学生時代にも自主制作みたいなことはしていましたけど、実は名古屋学芸大学に来て本格的に映画に関わるようになったんです。変な屈折の仕方をしながら関わるようになりました。ご本人がいるからあれなんですけど、渡部先生の元で映画に目覚めた、というか映画を新たに学ぶようになった。これまで映画というのは観るものであった。実際に映画を作ることに近づいたのは、渡部先生の下に付くようになってから、なんですよ。
渡部さんは。
■渡部眞さん(以下渡部):ぼくは凄く簡単で、高校の時に8mmを撮ったのがきっかけです。
高校で映画関係のクラブにいたのでしょうか。
■渡部:いえ、全く。友達と一緒にやろうと言って。大学も一応演劇科にはいましたけど、映画は自分でクラブを作っていたので、やっていたら、もうプロに行ったほうがいいんだろうって。で、見習いを。見習いのカメラマンになって、入り込んだんですよ。初めはコマーシャルですね。
一番初めに撮ったCMって覚えておられますか。
■渡部:一番初めですか。自分が撮ったのは、武田久美子のキャンパスリップ。かわいかったなあ(笑)。
そこから現在に至るまでを教えてもらえますでしょうか。
■渡部:それで、コマーシャルをやってて、その当時カメラマンになるまでには7、8年かかるのかな。それでチーフからカメラマンになったのが、29歳。ほぼ同時に映画の話があって。それが『の・ようなもの』。森田芳光の初35mm監督作品。それに合流したというか。いいタイミングでカメラマンとして入った。それが最初ですね。映画に入ったのは。
■柿沼:何年くらいですか?
■渡部:81年。84年にはアメリカに行ったんです。81年から83年まで栄光と挫折を(笑)。
アメリカに行かれたというのは、どこかの大学で勉強されたのでしょうか。
■渡部:アメリカのアメリカン・フィルム・インスティチュートという、大学院があるのね。そこに行って、もう一度やり直して勉強してこようと思って。
その時の勉強はその後の活動に多大な影響があったのでしょうか。
■渡部:凄いですね、やっぱりね。ある意味で吹っ切れた。色々な意味で。吹っ切れたし、色々な人と出会えたし、尊敬する先生にも会えたし、全てその後の映画制作から教育に携わることに恥ずかしさを感じなくなったのは、そういうきっかけがありますね。映像教育というのは、ありだなって。
院が終わって日本に戻られた。
■渡部:いえ。戻れなかったんです。20年くらいいました。ついこないだまで。まあ行ったり来たり。色々な映画やってたんで。帰ってきて日本のCMを撮ったりしていました。ベースは向こうで、行ったり来たりしていた。
■柿沼:本当、最近ですよね、戻ってきたのは。
■渡部:最終的にはね。八王子に来たのは。
ローアングルでワイドでしょ
ご自身の作品に関して、特徴やこだわりがあれば教えてください。
■柿沼:これは良いのか悪いのか分かりませんが、新しいものを広げようとするよりも、古典的なものに準じたいと思うところがあります。勿論昔あったものを再現なんかできないですし、そうすること自体には意味はありません。古典的な形式を持った映画を作りたいということです。
昔のものを再現していくことで、そこに新しいものが生まれるかもしれないという意識はありますか。
■柿沼:そうですね。風俗的に新しく見えるものは、すぐ古びてしまうと思っていて、むしろ過去にあるものの中に新しいものを見つけ出していこうとしているというのが正解かもしれませんね。映画というのは、ぼくが思うにですけど、概念みたいなもので、フィルムで撮ったら映画になるかというと、どうもそうではないらしい。アニメーションであっても「これは映画だ」というものはある。もっと広げればメディアは関係ないのかも知れない。どうやったら「映画」になってくれるのか、ということを考えながら作っています。
渡部さんはいかがでしょうか。
■渡部:まあ職業柄撮影なので、撮影に関して言えば。「スタイルはなんですか」とよく聞かれるのですが、ないです。あると仕事にならないんで。スタイルをなるべく持たないようにしています。で、映画で言うと、なるべくフレキシブルに。まず脚本の印象、ロケーションの強さ、役者の動き等々、目に見え、耳に聞こえ、肌で感じるものをまずベースに構築していく。これはもう、芝居に近いかもしれないですね。映像から作っていくタイプじゃないんで。あるものをどう再構築するということのほうが興味があるので、それによってスタイルといえばスタイルはある、かもしれない。まあしいて言えば、照明に関して、自分は無いと思ってたんだけど、独特だよと言われることがある。初期の頃は、森田監督とのコラボレーションだったのですが、結構ワイドアングルで下から狙うというのが、その時に結構多用していたもので、新人ではあったけど、それが面白いと言われて、結構仕事のクライアント筋から「渡部さん、ローアングルでワイドでしょ。あれやってくださいよ」って(笑)。そういう頼まれ方をしたことはありますね。
いつの間にか周りからそういうスタイルに見られていた訳ですね。
■渡部:その時たまたまやったスタイルで、そこを逃れようとして普通に撮る方法を一所懸命やったんだけど、それこそ難しい。珍しい映像を撮るのは意外と簡単なんだけど、もちろんいい演出家がいれば。標準レンズできちんと押さえて成立させるのは、それは相当な経験とちゃんとした撮影技術がないとできないですね。それはアメリカ行ったりして、段々そうなってきたもの。柿沼さんが言うように、過去の作品を観ると追いつけないなというのは多々ありますね。なにが新しいって、時間が新しいだけであって、ストーリーの構築とか撮影設定とかライティングとかっていうのは以前のもののほうが良かったりする。だから「本当にあんた新しいの」と言われれば「すいません、未だに超えられません」と答えざるを得ない。
一番大変なのは撮影に入るまで
監督として演技指導をされると思いますが、気を付けてること、大事にしていることはありますか。
■柿沼:「立ってください」とか「座ってください」とかいうことも勿論重要ですが、それよりもまずそのシーンにおける感情を大事にしています。現場に入るとこの時にこの登場人物はなにを考えているのかということをまず俳優と一緒に話し合います。「この時はどういう気持ちだと思いますか?」と聞くこともあるし、ぼくから言うこともあるんですね。お互いのそれがぶれないようにしたい。そこに関しては色々なやり方があると思う。映画はともすると、座っていれば座っているなりに映ってしまう。どういうつもりでも、狙い通りに見えてくれればいいという人もいると思います。でもぼくの場合はそこが一致していないとできないかなと思っています。やっぱりそこは同じ思いになっていたい。逆に言うと、気持ちさえ一致してれば、演じてくださる方たちというのは、動きの指示への抵抗が少なくなる。俳優はお人形さんではないので、そこは誠実に接しないと、ぼくのような若いというか、キャリアのない監督というのは、役者のほうが能力がある場合もたくさんあるので、うまくいかなくなります。
監督をしていて、一番大変なことはなんでしょうか。
■柿沼:クランクイン前日までです。こういう映画が作りたいって夢見ますよね。別に自分のものじゃなくてもいいですが、これを企画としてやりたい、というところから実際にカメラを据えるまで、ここまでが一番大変です。撮影や編集の苦しみはそれに比べれば凄く楽しいことです。ひとつの企画を、紙切れに過ぎなかったものが映画になる。現実的な問題が山のようにあります。そこが一番大変ですね。
撮影に入ってしまえば楽しい。
■柿沼:そうですね。あとは完成してからが大変です。どういう風に外に出していくのかということが。映画は興行ですから、学生と一緒に宣伝活動を行っているのですが、ぼくらも配給などやったことないわけですから、砂地に水を撒いているような。どれだけのリアクションがあるのか全く分からない訳で。蓋を開けてみないと分からないという。チラシをゴミ箱に向かって投げているんじゃないかと思うこともあります。これは本当に苦労、というか不安ですね。来ていただいたお客様が気に入って頂けたり気に入らなかったりというのは、ある意味不安じゃないんですよ。お気に召さない方がたくさんいるのも分かりますし、それはそれで受け入れられます。
『evidence』では役者のキャスティングに関わられたのでしょうか。
■柿沼:はい。極めてスムーズにいきました。
どういう経緯で今回のキャスティングになったのでしょうか。
■柿沼:ひとりひとり違うのでなんとも言えないのですけど、ひとことで言うと全員紹介ですね。ただ小林正和さんに関しては本当に別格で、「小林さんだったら大丈夫だ」と全員から太鼓判を押されて紹介されたので。で、実際大丈夫だった(笑)。
光で物語を作る
渡部さんはこれまで多くの作品に関わって来られていると思いますが、その中で最も印象に残った作品を教えてください。
■渡部:一番の出発点である『の・ようなもの』が大きいですね。初めてだからということもありますが、何も知らないでやったというのが大きかった。知ってたらとてもできなかったことを平気でやったり、いま考えたら恥ずかしいような。スタッフから馬鹿にされつつ、監督とふたりでコンテ書いていたあの時間というのが意外と貴重で、監督も今では巨匠面してるけど(笑)、あの時は「おい渡部どうしよう」って二人で泣きそうになりながらやったのを思い出すので。他にも色々ありますが、印象に残ったのは。
■柿沼:『誘惑者』は。
■渡部:そう、『誘惑者』は結構。アメリカから戻ってきて初めての作品が長崎俊一監督の『誘惑者』という映画だったんですけど、自分でもうまくいった。ある程度自分がコントロールできた、照明とか。向こうに行った理由は、照明がコントロールできない。ライティングがコントロールできなくて挫折して行ったんです。帰ってきてある程度できたので、逆に自分がやった失敗もあったんですが、それでも自分がやったという自負があったので、「これでやっと日本でもできるな」って思ったのがその『誘惑者』でした。これは余談ですけど、溝口健二のカメラマンの宮川一夫さんが監督にアドバイスしたことが入っていて、「光で物語を作る」というのがあったんですよ。カメラマンがこんなこと言うのかとびっくりしたんですけど。段々段々暗くなっていくと段々段々精神が病んでいく。そういうやりかたをしていて。室内に電気が戻るとぱっと意識が戻るという。照明と演出をカメラマンがこんなに作っちゃっていいのかと思ったんですけど(笑)、やっぱりすげえなと。それを基に脚本を書かれていたので、色々な意味で宮川先生の後を追って作った。そういう意味でも印象深かったですね。
目で見てると遅れるんですよ
一緒に活動するうえで、相手に持っていて欲しい能力や資質はありますか。
■渡部:一緒にやるには、まず、耳の良い人。目の良い人はいっぱいいるんだけど、耳の良い人はなかなかいないので。
音感がある、という意味でしょうか。
■渡部:そうではなくて、自分の職業から来ているんだけど、手と目が忙しい訳ですよ、やってると。で、次のことをやる時には耳を澄ましていれば必ずなにかの情報があるはずなんです。「次なにやろう」とか。誰かが言ってるはずなんです。それを聞かないとトンチンカンなことをやるので。職業柄なんですけどね。目で見てると遅れるんですよ。目で見て誰かがなにかを取りに行こうとした時に自分も行こうとしても、もう既に二歩くらい遅れている訳です。だけど「これやろう」と聞いた途端に動けば、誰よりも早く動けるんです。それを聞いてるか聞いてないかで、スピード、反射が変わってくるんです。反射神経の前に耳の良さが必要。それは意外と五感で知られていないというか。目で見てなにか一緒にやろうと思った時は現場では時既に遅しなんです。予測しないといけない。
■柿沼:聞いてないと遅れる。凄く良く分かります。耳が痛いです(笑)。
柿沼さんは。
■柿沼:ひとつは、理解力。必ずしも理解力とは言葉だけではないと思いますが、現場で起きていること、もしくはぼくがこうしたいと思っていることに対する理解力というものがもの凄く必要です。「あれ持ってこい」ということだけじゃないですからね。クリエイティブな場所というのは。こういう美術が欲しいというものに対して、必ずしも言葉だけで伝えられることばかりではないので、そういうものを含めた意味で。音楽なんかは一番分かりやすいと思います。言葉では説明できないことだらけですよね。担当部署に関しては、ぼくよりも、ある意味では物語だとか脚本を理解していなければならない。で、もうひとつは、やりたいことがあるということです。その作品に対して自分のやりたいことを持っているということは凄く大切です。それは常に最優先したいなと思っています。
もし、柿沼さんと違うイメージをもって参加された場合はどうされますか。
■柿沼:「これをやりたいんだ」という提示があって、初めて「違う」と言える。演出家の仕事というのは判断し調整するということなので、判断する材料を持って来て欲しいということなんです。例え違っていてもなにか持って来て欲しい。それがさっきの理解力の話に繋がるのですけど、理解力のある人はそれがぶれなくて、齟齬が少なくてすむ。言葉によるコミュニケーションも大事なんですけど、それだけではないなあと思う。口ベタであっても全然関係ないです。
意識の問題ということでしょうか。
■柿沼:そうですね。ある発見からなにがしかのコンセプトを抽出する能力が欲しいなと思う。
馬鹿になれ
監督として皆をとりまとめていくうえで、気を付けていることはありますか。
■柿沼:気を付けていることかどうかはちょっと分からないですけど、ある例を出すと、ロバート・ウィルソンが雑誌のインタビューで「ハイナー・ミュラーにひとこと言うとしたらなんですか」という質問に「be stupid!」と答えたんです。「馬鹿になれ」と。演出家でいるということは、必ずしも全てが論理的じゃないほうがいいような気がします。一から十まで論理で説明しても解決しないことがたくさんあるような気がしていて。ぼくは少し理屈っぽいところがあるので、あまり頭だけで考え過ぎないように気をつけています。人と対応する時も理屈で人を圧倒しないようにしようというか。それは自分で凄く気を付けようとしていることかもしれません。
論理的に接していた時よりも、円滑に物事は進むようになりましたか。
■柿沼:人にも寄ると思うんですけどね。理屈で納得しないと動けない人もいるので。逆に向こうからそういう風に来ることもあります。「あんたの言ってることは論理的に変なんじゃないか」って。そういう場合はそういう場合で接しますけど、今回の『evidence』の場合、スタッフに学生が凄く多かったので、彼らと気持ちを同じにするということもあって、ひとつひとつのことに素直に対応していこうというところはありました。あとは正しいとか間違っているということを価値基準にしないようにしようと思っています。とかく議論ってそうなりがちですよね。「こうこうこうでぼくが正しいだろ」ということで物事を進めていくことはなるべく止めたいなと。
議論云々よりも、相手をどう言いくるめるかという方向にいってしまいがちですよね。
■柿沼:それは現場ではあまり役に立たないというか。現実的に対処したいなと。
なんだか知らないが映画は面白い
映画の面白さ、魅力をどのようなところに感じていますか。
■柿沼:これ難しいなと思いました。というのも、ぼくはジャズや本も好きですが、映画だけは突出して面白い。この面白さはなんだろうなと思う。で、同語反復みたいになってしまうのですけど、映画の魅力というのは面白さなんじゃないかと思うんです。なんだか知らないが映画は面白い。
それは柿沼さんにとって。
■柿沼:そうです。ぼくにとって。映画はこれだけ芸術や文化や色々なものを飲み込んでなお面白い。これが映画の魅力じゃないかと思うんです。それはエンターテイメントという言葉で言い換えたくないんです。適当な言葉が思い付かないんですけど、アミューズメントパーク的な面白さではないと思うんですね。
■渡部:この間アニメーションプロジェクトといって、皆でアニメーションの話を教員、助手全員でやったんですよ。そこで山村浩二さん、アニメーション作家の、が来て、「アニメーションというのはコマとコマの間にはなにもない」って話をしていたんですよ。ぼくが映像に入るきっかけは、高圧線が新興住宅地に通っていて、歩いていると線が入り交じるんです。それは結構鮮明な映像体験であって。小学校まで40分くらい歩く道だったので。それを見ながら帰っていた記憶があって。その運動、動きの面白さというのはいつも気にしていたんですよ。そこには現実の連続した世界があるんです。でも山村さんの話はそうじゃない。それでびっくりして。アニメーションの人はこんな風に考えてるんだと思って。じゃあ逆に我々はどうかというと、リアルな世界の中で全てが繋がっている。立体や空間とも全てが繋がっていて、それを記録する為に映画を考えていたのに、そうじゃないって考えている人もいるんだと。映画の面白さはストーリーの面白さと、映像そのものの写真的な面白さもあるんだけど、動いているというのがぼくにとってワクワクする体験なんですよ。だから、分断しているといいつつもアニメーションも面白く感じるし、演劇から入ったというのもあるけれど、役者の表情とか、声の質とかトーンとかいうところで、要は人間を捉えるというところになるんだけど、その面白さ、全身で感じ取るというね。そう思います。
表現したいことは意外と昔から変わらない
映画で最も表現したいことはなんでしょうか。
■柿沼:ぼくなりの考えですが、映画というのは、色々な異論もあると思いますけれども、最終的には「物語る」面白さだと思います。どんなに不条理で吹っ飛んでいたとしても、それは物語に対する面白さではないかと思っているんですね。映画というのは人生と繋がっている。地続きである、あって欲しいのかもしれないです。でも、自分が人生の中で生きているということと物語は必ずしも同じではないですよね。物語のように生きている訳ではないので。なので、物語を語ろうとする時に、自分の人生の地続きとして語ろうとするとひずみやゆがみが出てくる。そのひずみやゆがみというものに、最終的に打ち勝ちたいという気持ちがある。自分の人生というのをそのまま反映している映画というのもあります。淡々と日常生活が続いていく。そういう中に良い映画も沢山あると思ういますが、それをぼくはあまり良しと思っていなくて、やはり映画には飛躍があって欲しい。ただ、それが本当に飛んでしまっていると、やはりいけないなと思う。そこにあるひずみに物語が勝ってほしいと思うんですね。その溝を埋めるのが映画で、自分が表現したいことなんじゃないかと思います。それが演出する、映画を監督するってことじゃないかと思います。どんなにSFのような作品であっても、やはりそれが人生の中の地続きであることには間違いない。それをどうやったら埋めていけるだろうか。物語の世界があって、人生がある。そこに飛躍があって、そこを飛ばすのが映画なんじゃないかなって思うんですよ。
渡部さんは。
■渡部:立場によって違うんだけど、撮影者としてじゃあ表現をどうするかというと、まずは監督がなにを求めているかというのが大きいんですよ。他者としての監督がいて、それをぼくがなぞるというか、後付けするというか、慮るというか、なにかしら想像力をきかせながらそこにアプローチするじゃないですか。それは結構面白い作業なんですよ。今回は固い感じでいったほうがいいのか、少しフラットな感じでいったらいいのか、そういう自分の中にある技巧を駆使して、監督の中にあるアイデアと合致させる。次に自分が監督としてやることもあるので、それはどうするかというと、もちろんひとつのストーリーに対してどのようにアプローチしていくかというのは、自分の考えている妄想をいかにうまく作っていくかということなんだけど、果たしてこれは表現という言い方をしていいのかなと思う。つまり、自分の中にあるものを外に出していくように見えるんだけど、まず物が先にあるじゃない。それを映すことによって再構成していくというか、話を作っていく訳でしょ。だから全く無から表現している訳ではないですよね。もちろんストーリーラインというのがあるんだけど、例えば黒い空間にいるのと、白い空間にいるのとでは思い付くことが違う。もちろんそのチョイスは我々にあるんだけど、表現することがその都度変わっていってしまう。その曖昧さがある意味好きなの。曖昧さ、いい加減さ。人の力を借りて、例えば昔のゴシック建築とか借りて表現するじゃないですか。自分では積み木くらいしか作れないのに。人が作った何百年か前の建築を前にして。それを含めたいい加減さ。引用だよね。引用ということによって表現しようという。だから新しいんだよね、きっとね。いつの時代も映すものが新しくなれば映画が新しくなったように見えるから。そういう意味では気楽は気楽。でもストーリーラインというのはまたちょっと違ってて、神話とか民族学的な話ってこう、万人に共通な愛の話ばかりじゃないですか。そういうことをベースにしていくことはもう何千年と変わってない。だけど、纏う衣装が紫式部の時代とは違っていて、十二単着てなくて、そういう現代風のね、ものを着てる訳でしょ。それが新しく感じて。新しいスターを使えば新しい映画だとは言うけど、そこにあるのは古代からの焼き直し。でもそれでいいと思う。「新しい」という言葉は魔物。それによってごまかされる。まとめると、ようするに纏っているものは色々と変わるけど、表現したいことは意外と昔から変わらないところがあるってことかな。
これで質問は終了です。ありがとうございました。
■柿沼・渡部:ありがとうございました。