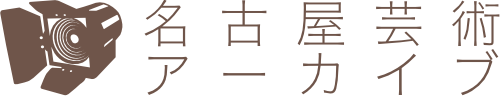犬の5
まずは佃さんが演劇を始めたきっかけを教えてください。
■佃典彦さん(以下佃):元々は小学校の学芸会。5年生、いや3年生か。ぼくは成績も良くなかったし、凄い虐められっ子で、運動もできない。学校に行っても来てるのか来てないのか分からない。とにかく先生に褒められるということがなかったんですけど、お芝居やることは好きで、3年生の学芸会の時に『王様の剣』というお芝居をやりまして、アーサー王の物語で、剣を抜いたものが王子様になれるという。ぼくは「犬の5」という役で。
良く覚えていましたね。
■佃:ほんと(笑)。台詞がひとつだけで、「ワート早くおいでよ」。で、それを言った時に、浅井先生という女の先生が「あなたうまいわねえ」と褒めてくれて、「みんな佃君のように台詞は言いなさい」って褒めてもらって。その時に人生が決まったなって(笑)。小学校6年生の時の卒業アルバムには「将来は役者になりたい」と書いてあるんですけど。でも思ってるだけで、中学高校と剣道部で演劇と全く関係ないまま過ごしました。で、大学入って、同じクラスになった水野君。凄い大人しそうな人だったんだけど、彼が演劇部に入るって言うので、付いて行ったんです、部室に。そしたらそのままの流れで入ってしまって。名城大学劇団獅子。でもそれから。
その時は役者として。
■佃:役者として、ですね。
そこから脚本を書き始めたきっかけは。
■佃:それはですね。劇団獅子ってサークルは、オリジナル作品をやるという伝統で。既成の台本はやらないんです。ぼくが入った時に、4年生の男の先輩が本を書いていたんですけど、卒業していなくなるじゃないですか。大学の2年の時に誰かが本を書かなきゃならない状況になって、誰も立候補しなかったので、じゃあジャンケンだと。ジャンケンで負けた奴が書くことにしましょうと。ジャンケンポンと、ぼくだけチョキで、皆グーで。一発で負けたんです。で、ぼくが書くことになりました。
その時の台本はどのような話だったのでしょうか。
■佃:その時は、場所が岡崎の刑務所だったんです。それは演劇部の中に刑務官の娘が居て、慰問で演劇をやって欲しいと。それが最初だった。当時あれは旅芝居の一座のお話を書いたんですね。タイトルも忘れちゃいましたけど。
反応はどうでしたか。
■佃:2時間くらいで長かったんです。2時間以上あったかな。最初のうちは拍手とかあったりして。医療刑務所だったんです。なにやっても笑うわけなんですよ。人が出てすっ転ぶだけで大爆笑。女の子が出てくると「ヒュ〜」って。最初のうちは良かったんですけど、段々、閉め切られてるし、暑いし。そんなに長い時間やるとは向こうも思ってないので。そのうち耐えられなくなって「あ〜!」って奇声を発し出す人がいると、刑務官がダーッて来て取り押さえたり。皆暑いから服を脱いでいくじゃないですか。そしたら入れ墨だらけで。やりながら「ああ、ここ刑務所だったんだ」って。まあそれで終わって、ありがとうございましたって読み上げてもらって。感謝状を頂いて。というのが、ぼくの最初の演劇の、作演出でやったものでした。ぼくの処女作は刑務所で囚人の方々が観てたんです。
ぼくが名古屋の演劇状況を変えてやるぞ
B級遊撃隊を立ち上げた経緯を教えてください。
■佃:大学の演劇部でずっとやってて、ぼくが劇団獅子に入った時はお客さんも少なかったし、「名城大学に演劇部まだあったの?」と言われるくらいになっていた。ぼくの入った時に、わりかし男連中が揃って、ぼくが脚本書いてやるようになって、とにかく名古屋の大学の中で一番になってやろうと思って。ぼくの中では3年、4年の当時には1番になっていただろう、と自負はしているのですけど、動員数的にも。でまあ、天狗になってまして、かなり。卒業する時に就職も決まったんですけど、そこを蹴りまして、B級遊撃隊を旗揚げし、その時は、ぼくが名古屋の演劇状況を変えてやるぞ、みたいな意気込みで旗揚げしたんです。
当初は何人くらいいたのでしょうか。
■佃:男6人。
皆さんも同じような意気込みで。
■佃:そうですね。皆そんな意気込みでいましたね。で、当時80年代の終わりくらいですから、世の中もバブルの入り口で景気も良かったし、とにかく就職に困らなかった。学生が。プータローと呼ばれていた人たちがフリーターという名前になって、大学卒業して2、3年好きなことやっていてもまだ就職口はあるぞという頃だったので。フラフラしてる人は多かったですね。
それでも許された時代なんですね。
■佃:許される空気が世の中に蔓延してる感じはあって。まあ旗揚げして。でも親には反対されたんです。就職も決まったのに。母親には木のハンガーで殴られ。頭から血を出して。「裏切り者」と言われて殴りかかってきましたから(笑)。親に黙って就職蹴りましたからね。その時に親に、旗揚げして3年以内に東京公演。それから名古屋で動員1000人にいかなかったらやめますと。そして始めたんです。
それは果たせましたか。
■佃:果たしました。25の時にシアターグリーン。名古屋での動員は1500〜1600くらい。あっという間に動員は増えました。
凄いですね。
■佃:凄かったです。振り返ってみると、そんなに面白いことやってる訳じゃないんですけど、男6人しかいないということと、『ゲンコツ芝居』っていうキャッチフレーズを付けて、とにかく動いて叫んで、毎年夏には鶴舞公園で野外劇をやって。あとは『審判』ていう一人芝居がありまして。第3回名古屋文化振興賞、それで入選したのがぼくが23の時だったんです。それを北村想さんが演出してくれて、伊沢勉さんがやるという感じで、鶴舞公園の野球場でやったんですね。それは想さんが「佃野外でやってるから本当に野外でやろう」って言ってくれて、野球場にお客さん入れて、審判のところに役者立って、一人芝居をやったんです(笑)。
お客さんはどこにいたのでしょうか。
■佃:マウンド辺りに。わーっと。
勢いがあったんですね。
■佃:勢いありましたね。そんなこともあって、動員も増えていったと思うんですけど、そのままずっと今に至る。
賞を穫ったというのも大きいと思うのですが、劇団が大きくなっていった要因というのはなんだと思いますか。
■佃:当時男6人という劇団がなかったということと、『ゲンコツ芝居』というキャッチフレーズを付けたこと、夏は鶴舞公園、冬は名演小劇場、それを3年間続けた結果なので、それはうまくいったんだろうなと思います。なんか当時やたら元気のいい馬鹿な男の子が出て来たなという目で見られましたね。
B級遊撃隊の名前の由来を教えてください。
■佃:さあ劇団を旗揚げしよう、という時に、名前をどうしようかと。で、B級というのはね、早い段階で決まっていて。それは何故かというと、当時、ぼくの好きな映画が所謂B級映画だったんです。例えば、駅前シリーズだったり、社長漫遊記だったり、クレイジーキャッツの映画だったり。
邦画が中心だったんですね。
■佃:邦画好きですね。『零戦燃ゆ』とか『二百三高地』とかはA級。だけど、日活のアクション映画とか、B級というのが好きで。遊撃隊というのは、普通にごちゃごちゃ話しているうちに、威勢のいい名前がいいな、男6人なので。そういうことで付けたんですね。
合議の上で。
■佃:んー。いくつかぼくが候補を挙げて、これがいいねという風になったと思います。B級は決めていましたから。
締切きっちり守ります
脚本というのは、その人の癖みたいなものが出ると思いますが、佃さんにしかない特徴はありますか。
■佃:まずひとつは、早いということ。締切にはきっちり出す。締切には台本上がっている。
ぼくがB級遊撃隊のホームページを見させていただいて、一番感動したのは、「締切きっちり守ります」と書かれていたことです。
■佃:それはちょっと自分の中では、枷としているところでもあります。そもそも役者なので、それが大きいと思います。ぼくだけ後の構想を知っていて、他の役者が分からなくて、なんかずるい気がして(笑)。役者やってるのは大きいかな。作演だけやってれば稽古しながら本書いたりとか。ぼくは役者がやりたいというのが大きいので。自分の劇団でもそうしているし、劇団さんに書き下ろしたりする時も締切は守る。そういう風にはしています。
無茶な締切を振られることはありませんか。
■佃:稽古初日までに上がっていればいいので。想さんほどじゃないですけどね。あの人は半年以上前に上がっているから。あそこまでではないです。
でも、凄いです。
■佃:本の内容的なことを言うと、不条理系とか、ぼくは系統的にはそっちだと思っているんですけど、日常の中にどういう妄想を放り込めるかなというのは思っています。妄想っていうところが、ぬけがらを脱いでみたりとか、家の天井から土管が突き出ているとか、性犯罪者ばっかり集めた街があるとか(笑)。
そういうアイデアはどこから生まれてくるものでしょうか。
■佃:安部公房とか、カフカとか、赤塚不二夫の影響だと思います。
そんなことをしてはいけません
失礼な言い方かもしれませんが、佃さんは俳優としても実力のある方ですね。
■佃:元々は役者さんなので。ジャンケンで負けたから書いてるだけなんです(笑)。
とても自然に舞台に立っているなという印象を受けました。
■佃:それは心掛けていますね。
どのように役作りされているのでしょうか。
■佃:気持ちは考えない。役の。内的要因はほとんど考えなくて、考えるのは外的要因。
気持ちを作ったりしないということでしょうか。
■佃:しない。しないし、ぼくが外で演出する時も、「そんなことをしてはいけません」と言います。
それには理由があるのでしょうか。
■佃:人間の感情が動くのは外的要因に依るだからです。だから外的要因を考える。外からなにが影響されているか。リアクションによって観ている人は、この人どのような気持ちでいるんだろうとか見えてくるし、役者自身もリアクションによって掴む事ができる。
それは相手の台詞とか。
■佃:相手の台詞だったり。まあ言ってみれば、太い、細いとか、所謂『デニーロ・アプローチ』。あれも外的要因。髭が生えているとか。髭がモサっと生えている自分と、髭を剃っている自分って違うじゃないですか。太っている自分と細い自分も違うし。プラス、相手。人との距離だとか。台本に「凄く寒い場所」と書かれてあれば、それは外的要因。というところから作っていく。作るというか、その中に自分を放り込むという感じかな。
放り込んで、その状況に素直にリアクションしていく。
■佃:そうですね。
愚直にも同じことを続けようという意志
B級遊撃隊では神谷尚吾さんが演出を担当されていますが、佃さんが演出をするのは外部活動のみでしょうか。
■佃:外部のみというか、ぼくが役者をやらない時。役者と演出を兼ねるのが嫌なんです。昔は作演出、出演とやってたんですけど、もう今は演出出演兼ねるのはちょっと。無理というか。
演出の際に意識していることはありますでしょうか。
■佃:まずは、先程の役者をやる時と同じで、気持ちから入るなということ。ぼくはある程度、芝居は物理で作ることができると思っているから、外的要因から作るということですけど。距離とか、具体的に台詞を誰に当てているのか。ベクトル。ベクトルの方向と大きさ。そこをきちんと積み重ねていけば自ずと関係性は取れてくるかな。それだけじゃないんだけど。素人さんを相手にすることが最近多いので、まずはそこで形を作っちゃう。ということが多いので。気持ちを入れようとするんですね、素人の方は。如実に。それはしないでと。
では、自分が役者でやろうとしていることをそのまま。
■佃:そう。だからぼくは演出家じゃない。ただ役者の演技指導に毛が生えたような。あとは照明にしろ音響にしろ舞台にしろ、いつもぼくが付き合っているスタッフさんに相談している。
どのような役者となら一緒にやりやすいと考えていますか。
■佃:やりにくい人は、自分でお芝居作っちゃう人。一人で。だから内的要因で芝居作っちゃう。台本から気持ちを、感情の流れを汲み取って芝居を作っていこうとする人は駄目。
逆に言うと、やりやすいのは相手との関係性から作っていける人ということでしょうか。
■佃:そう。後は周りの変化に敏感な人。昨日の芝居と今日の芝居は違うでしょ、ということに敏感でありつつ、愚直にも同じことをやり続けなければいけないんです、役者は。その辺のことがちゃんと分かっている人。
折り合いが付けられるということでしょうか。
■佃:愚直にも同じことを続けようという意志というのは、言い換えると、昨日の芝居と今日の芝居が違うということを分かっている。
違うという意識があるから、同じという意識が生まれる。
■佃:そう。その辺を分かっている人とやると面白いですね。演出というよりも、役者としてやる時ということになっちゃいますけど。
ちまちまちまちま
シニア演劇部等、外部の活動も積極的にされているということで、少し小難しい話になりますが、社会における演劇の位置付けというものをどのように考えていますでしょうか。
■佃:一言で言うと、演劇というのは、世の中、社会の中で無駄なものである。あってもなくても全然いい。無駄だから、それが尊い。あってもなくてもいいものが世の中にいくつ存在することができるかってことが、文化だと思う。経済理論から言うと舞台にしろ、おそらく絵もそうだと思う。音楽は少し違うけど。一生のうちに一回も美術館に行ったことない人いるだろうし、ましてやお芝居をいっこも観たことない人は。ぼくは自分でやってるから観るけど、ぼくやってなかったら七ツ寺共同スタジオなんて行くこと一度もなかった(笑)。だからなくてもいいんです。でもそれがいくつ存在するのかということが文化で。だから演劇というのも無駄なんです。今シニアの方とかお仕事を終えられて、定年されて、なんかやりたいな、なにしようかな、チラシ見て、「演劇か、俺昔演劇部だったな」とか、一度もやったことないけど挑戦してみようとかという方々がほとんど。
ちょうどいい感じで(笑)。まさにこういうことなんじゃないかな、と今感じました。
■佃:無駄なことができる喜びなんだと思う。
凄い分かりやすかったです。仕込みかと思いました(笑)。
■佃:ぼくら演劇人なんかはようするに最初から無駄なことに足を突っ込んでやってる訳で、無駄なことをすることによって喜びを得る人がいてくれることは嬉しいなと。
演劇の面白さ、魅力をどういう所に感じていますでしょうか。
■佃:それぞれね、本書きとしての面白さとか、役者としての面白さは違うんですけど、劇作家としての面白さは、究極の一人遊びである、というところ。
作家はひとりでいるのが好きという印象はあります。
■佃:究極の一人遊びであるということは、最後まで一人で書くということなんですよ。だから稽古場に行って、稽古しながら台本書き上げていくとか、ぼくにとって面白い作業ではない。
当て書きはしない。
■佃:当て書きはします。するんですけど、書く作業を現場に持ち込みたくない。ぼくが一番好きな時間というのは、台本を書き上げて、大体閉め切りの一週間前に書き上げる。その書き上がった台本をちまちまちまちま直すのが好きなんです。細かい所とか。ちまちま直すのが好きなんです。出来上がったプラモデルを、ここの塗装をもうちょっとこうしてみようかな、とか。その時間がもの凄く好きなんです。
逆に辛い点はありますか。
■佃:辛いのはね、そうだな、台本がなかなか書けないのは辛いんだけど、それも返してみれば創作の喜びのうちに入るだろうから。人間関係かな。劇団辞めますとか言われたら辛いとか、そういうことかな。それは演劇じゃなくてもそうなんだろうけど。
自分が思うのは、作家さんは一人でいるのが好きな方が多い一方で、演劇に関わる以上、人とのコミュニケーションを取らざるを得ない。その辺を皆さんどう折り合いを付けているのかと。
■佃:ぼくもそう思うので、演出する時も、自分で書き上げてからじゃないとできない。
辛いことよりも、それ以上の楽しさがあるのでしょうか。
■佃:演出に関しては喜び云々はまだよく分からない。ドキドキハラハラするしかない(笑)。さっきみたいに終わった後に喜んでもらえると嬉しい。
実験場
佃さんが演劇で最も表現したいことは。
■佃:なにかなあ。あれもこれも色々あって。最近興味があるのは、全く日常から離れた場所で、最も日常的なことを表現したい。例えば荒野の真ん中だとか。これは次回作の構想があるから言ってるだけかもしれないけど。
じゃあこれを出したらまずいのでは。
■佃:いえ、大丈夫ですよ。荒野の真ん中で風が吹きすさぶ、赤い荒野(笑)。そこで日常的なことが表現できないかなあ。
砂漠の真ん中でお茶の間を再現するとか。
■佃:そんな感じですね。
最後にB級遊撃隊の見所を。
■佃:毎回、劇団での作業は、ぼくにとって、神谷にとってもそうだけど、実験場である。なにかを実験する。でも実験演劇にはしたくない。どういう実験の場であるかということを、観て欲しいので。実験というのは集団の意志。我々がなにをしようとしているのか、我々がなにに興味があるのかを観て欲しい。自分自身が期待していることでもあるんだけど。その中で、独りよがりではどうしようもないので、そうありつつも有り体に言えば分かりやすくしたいとは思っています。
そういう意識は劇団内で共有されているのでしょうか。
■佃:本公演以外に合間があるじゃないですか。通常稽古とかやりますが、演出の神谷がいまどんなことに興味があるとか、舞台上でこんなことをやりたいとか、またはぼくがこんなこと考えているんだけどとか、そんなことを出しつつ、役者の中でもこんな事に興味があるとか。日頃やってる中で話し合って、ぼくが台本を書く時に、それがうまく出せそうなら。この前の『ガードマンの恋』もそうだけど、蝋燭の明かりだけでやってみたいとか。稽古やってる中で怪談話やってみようとか。それはプロデュース公演ではあまりできないので。
通常稽古というのは、本番に向けた稽古ではなく、役者の技術的な。
■佃:発声練習やったりとか、ちょっと歩いてみようとか。歩いて出会って、こっち向いてとか。
名古屋でそういう劇団ってあまりないですね。
■佃:劇団が少ないですね。ユニットが多い。
そういう現状についてはどう思いますか。
■佃:ぼくは常々、東海支部の若い劇作家たちへは、ユニットではなくて劇団にしなさいと。ユニットというのは好きじゃない。
ちゃんと続けられる所を。
■佃:鍛えられないです。何本やっても。特に作家。鍛えられない。それは劇団でやらない限り。自分の好きな人数で、自分の好きな役者だけで芝居をやっても。劇団と言ったら毎回同じ人数で、この公演も次の公演も、同じメンツで、枷があってやる訳だから。そういうのがないと、駄目。だからきちんと成長していく人は劇団を持っている。
今日は長い時間本当にありがとうございました。
■佃:ありがとうございました。