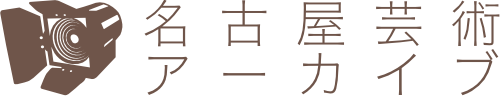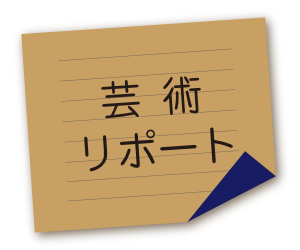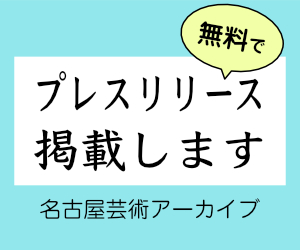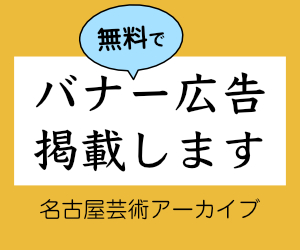ないんですよ
まずは刈馬さんが演劇を始めたきっかけを教えてください。
■刈馬カオスさん(以下刈馬):これがですね、ないんですよ。
ない?
■刈馬:中学の頃から、ぼくは役者をやりたいと思っていたんですね。ただそれが、なにをきっかけに役者を志そうと思ったのか、覚えていないというか、当時もきっかけがなくそう思ったんです。
テレビや映画を観てではなく?
■刈馬:普通にテレビや映画を観てたけれども、こういう世界に入りたいという憧れはなく、いきなり、よしなろうと、自分はこっちに進もうと思ったんですね。
そして高校から演劇を始められるんですね。その時は役者としてでしょうか。
■刈馬:役者でしたね。役者をやりたくて。同期に、今は大阪でデス電所という劇団を主宰している竹内佑というのがいて、彼が演劇の先生でしたね。その後、大学でも一緒で、つるんでたわけじゃないけど7年間を過ごしました。
大学ではどのような活動を。
■刈馬:近畿大学の文芸学部にある、演劇芸能専攻というコースで。
サークルとかではなく、専攻として演劇を学ばれていたんですね。
■刈馬:そうですね。学校の授業として演劇を。
この頃は役者をされていて、今は作演ですよね。どういう流れで変わっていったのでしょうか。
■刈馬:高校の演劇部が凄く弱く、地区大会でいつも敗退してしまう学校だったんだけれども、なんとか上の大会まで勝ち進みたいと頑張って、3年生の時に中部大会で準優勝したんです。非常に達成感があったんですが、その翌年、自分らが卒業した後、後輩たちが地区大会であっさり落ちたんですね。で、これはいけないと。でも、うちの高校は当時男子校で、男ばっかりでやろうと思ったら、プロの台本はなかなかないですから。だから自分たちで書くしかない。じゃあ練習用の台本を書いてあげるよって、ぼくは全く書いたことなかったんですが、見よう見まねで一本書いて。そしたら、後輩たちが次の地区大会で上演する台本が他になかったから、この台本を選んで。それで初めて上演されることになったんですね。
結果はどうだったのでしょうか。
■刈馬:中部大会まで行きました。その時は今のぼくからは全然想像もできないと思うんですけど、ワンシチュエーションコメディーだったんです。三谷幸喜のような。で、県大会の上演終わった後に、当時の審査員だった佃典彦さんが「脚本書いたの誰」って。そこで褒められたのが嬉しくて、じゃあもう一本と続けていくうちにまあずるずると作演のほうへ入っていったという流れで。
その後青年団に入られていますが、その時は俳優部ですよね。
■刈馬:役者をやりたかったので。作演を評価されるのが凄く複雑だったんです。嬉しい一方で、自分がやりたいのはこっちじゃないと。それで思い切ってやめようと思ったんですね。で、青年団のオーディションを受けたら幸いなことに合格したので。それから東京に行って、青年団には1年間役者として所属していたんですけど、もうどうにも自分の下手さ加減に辟易してしまったりとか、平田オリザの駄目出しを受けた時に、なるほど、こういう風に駄目出しするのかと、役者としてではなく演出家として勉強するようになってしまっていたんです。それでこれはいけない、駄目だなと思って。その時にちょうど七ツ寺共同スタジオ30周年記念事業の作演出の話を貰ったので、名古屋に帰ると同時にその仕事を引き受けて、劇団を始める準備に入ったと。
それがメガトンロマンチッカー。
■刈馬:そういうことですね。
そしてメガトンロマンチッカーを経てテラ・インコグニタ立ち上げになる訳ですが、テラ・インコグニタの名前の由来を教えてください。
■刈馬:ラテン語で「未知なる大地」。どうやら使われる場所としては、研究職の人たちが新しい発見に挑もうとする時に、その対象のことをテラ・インコグニタって言ったりするとかしないとか。どのくらい普及しているのか、ぼくには分からないのですけれども。
言葉の意味に惹かれたのでしょうか。
■刈馬:いや、言葉の意味は全然(笑)。実験的なお芝居にこだわっている訳ではなくて、ただどういうお芝居をやる人にしろ、新しいなにかを作りたいという欲求であるとか、世間的には使い古されたことであるかもしれないけれど、自分なりには新しい挑戦であったりとかっていう新陳代謝を活発にしていかないと、表現者としてすぐに廃れてしまうとぼくは思っています。ですから、常に自分なりの未知なる大地を目指し続けるということは、特にぼくに限ったことじゃなく当たり前のことだと思っていて。だから劇団表現者とか、そういう名前と同じだとぼくは思っています。
目的と対象
これまで刈馬さんと話す機会があって、いくつか印象に残った言葉に「目的と対象」「表現ではなく存在する」というものがあったのですが、その言葉の意図を教えてください。
■刈馬:基本的にお芝居というものは台本を基にして作りますし、ぼく自身は劇作家でもあるので、自分の書いた台本を基に舞台にすることが多いのですけれども、ただ、その台本に書かれた言葉というものを、ただ漫然と言っていれば、ただ順番通りに言っていけばお芝居は成立するかと言えばそんなはずはなく。その言葉を言う為には、それなりの動機であるとか、場の流れとか、感情であるとか、文字に書かれたもの以外の、いわゆる行間に埋まっているものが大事なんですね。そこをちゃんと見ないと、どうしても文字っていうのは力が強いので、引っ張られてしまうんですね。そこを気にしようという合い言葉として目的と対象という言葉を使っているんですけれども。誰に向かっていうのか、なんの為に言うのかってことですよね。
演出をする際、その目的と対象という言葉で役者に意識付けをされていると思うのですが、それ以外でその意図を伝える為にされていることはありますか。
■刈馬:どうやったら相手に影響を与えられるかってことをぼくはよく言うのですけど。極端に距離を縮めてみる。極端に離れてみる。声を大きくする、小さくする。間を取る、とかそういう色んなバリエーションを色々試させてみます。ぼく自身も自分で書いた言葉というのは思い入れがあるし、文字に捕われてしまうので、敢えて実際の稽古では、本番ではやらないような距離で話したり、そういうことをすることによって、この台詞ってこういう意味にもできるんだ、こんな台詞にしたらこんな風に人間関係が変わるんだ、という発見をする。とにかくひとつ簡単な、「ごめんね」という台詞でいいんですけれども、とことん作ってみると、台詞に対する姿勢というのが変わってきますね。ぼく自身も、役者も。そうすると他の台詞にも影響するので。
表現でなく存在する、というのは。
■刈馬:フリをする人が多くて。怒ってるなら怒ってるフリだとか、悲しいなら悲しいフリだとか、そういう、それっぽいことをする人がいて、でもお芝居ってそうじゃないんですよね。それがもの凄いうまい人だったらいいんですけど。悲しいフリをするんじゃなく、あなたがこの場で悲しくなりなさいって話なんです。そして、その場で悲しくなるにはどうしたらいいのか。そしたら、相手の役者との関係性なんです。具体的にその場面以前の部分を突き詰めて作っていくと、自ずとその台詞になった時に凄い悲しい気持ちになれる。
その瞬間に悲しくなるのではなく、悲しくなるその経緯をちゃんと作れば、自然と悲しくなる、ということですね。
■刈馬:やっぱり理由がある訳だから、それには。だからその理由ってものをちゃんと作らなくっちゃいけないけど、役者は台詞をどういう風に言うのかを考える人が多くて。でも、それは表現なんですよ。ではなくて、その場でちゃんと悲しい気持ちになる為の環境を整えてあげる。
文字の情報から解き放たれる
青年団の特徴のひとつである「意識の分散」について、青年団出身の刈馬さんなりの解釈などがあれば教えてください。
■刈馬:ぼくの場合は、台本に書かれた文字の情報から解き放たれる意味で、意識の分散を使いますね。例えば相談するシーンだったとして、字面だけみたらこの人は本当に真剣に話を聞いているようにしか見えないんだけれども、意識の分散をさせると、別に全然話を聞いてなくても相槌なんて打てるものなんだ、話を聞いてなくても「そりゃ大変だ」とか言えるものなんだと。そういうことが分かったりすると、文字に書かれた世界というものから自由になれるんですね。最終的には凄く真剣に話を聞く人に戻ってもいいんだけれど、最初から選択肢が一個しか無い状態になっちゃうのは不健全だとぼくは思う。できるだけ選択肢を揃えた上でひとつ選ぶ作業をするべきだと思う。
演出するうえで、刈馬さんが気を付けていることはありますか。
■刈馬:台本に書かれた文字の情報とどう向き合うか。文字に捕われすぎず、文字をないがしろにし過ぎず、どう立体化していくか。もうひとつは空気を作ることですね。本に書かれている言葉の全てが全て分かりやすくなっている訳ではないんですね。じゃあそれを舞台の上に乗せる時に、どうやって分かりやすくするのかとか、どうやってお客さんに伝えようかとか、伝える手段として色々あるんですけれど、ぼくが一番大事にしているのは空気ですね。そういう空気を表現できるのが演劇の面白さだと思っていて。だから空気を作る。空気をベースにして、台本の世界や言葉をそこに浮き彫りにさせる。作品を作るうえでそれを大事にしています。
役者に求めるものはありますか。
■刈馬:受け身にならないことですね。指示待ちになるというか。単純に面白くないし、ぼくの感性だけで作れるほど演劇は甘くないです。色んな人の感性が混ざって、それを調整していくのがぼくの仕事だと思っているので。どうしたらいいですかって感じになるよりも、先に動いて欲しい。
自分で考える力ということでしょうか。
■刈馬:考える力が有る無しではなく、お芝居をするにあたっての姿勢の問題だと思う。そして、書いた僕自身が驚くような解釈や読み方をしてくれる、発見をもたらしてくれる俳優がいると嬉しいです。
書いた台詞をそのまま使うことにこだわったりはしませんか。
■刈馬:台詞によってはこだわるし、こだわらない台詞もある。稽古の過程で変えることもたくさんあるし、できるだけ柔軟に考えたいとも思ってます。そこを見極めるのも演出の仕事ですけど、なかなか難しいですよね。
余韻のある作品を作りたいので
脚本についての質問になります。いくつか作品を見せていただいて、時事ネタが多い印象がありましたが、その辺は意識されていますか。
■刈馬:時事ネタを扱っていこうという気持ちは全然ないんですね。
結果的にそうなっている。
■刈馬:普通に社会で生きていく中で色んな情報が入ってきて、その情報の中で引っ掛かったものをピックアップして書いているだけで、作品で時事ネタを解決しようとか、そういったことを考えている訳ではなく、それらを使うことで、ぼくらの普遍的な問題に向かい合おうと。例えば、佐世保小6同級生殺害事件をあつかった『モンスターとしての私』であれば、何故人を殺しちゃいけないのか、であったりとか。
脚本のアイデアはどのようにして生み出していきますか。
■刈馬:色々ですね。身障者専用デリヘルをあつかった『マイ・フェイバリット・バーーーーーージン』では、日本での風俗産業っていうのが世界に類を見ないほどバリエーションがあるので、それらを一度書きたいなって。
風俗を扱いたいと思ったんですね。
■刈馬:風俗のことは見て見ぬふりをするけど、性の問題は生きていく上で避けて通れない。他の国では何かのプレイに特化した店なんてそうそうない訳ですよ。そういう細分化されていく、痒いところに手が届くというのが日本的だなと思って。しかもイメクラがあるばっかりに、それまで普通に生活していた人が、コスチュームプレイに目覚めてしまうとか。環境があるばっかりに、その人の内面にある欲望が浮き彫りになってしまうということもある訳ですね。需要があるから供給があるじゃなくて、供給があるから需要が生まれるみたいな、逆転も出てくるんじゃないかと。最終的にそういう物語にはなっていないんだけれども、スタートとしてはそうでしたね。
『恋愛耐湿』ではPKOを扱っていましたね。
■刈馬:あれは修羅場の話にしようと。で、ぼくの舞台は照明やセットが凝っているのが特徴なので、それを一度全部取っ払おうと。音楽使わない、照明使わない、装置はバスタブ一個だけ。役者の出入りも一切ない。で、50分行く。というルールを自分で決めてやったんですね。それで、それをどういう風に転がそうかと考えた時に、絶対大丈夫だから、安全だからと合コンに行ってきた彼女が浮気して帰ってきた、ということが過去にあったという設定から、何故だか分からないけど、それはPKOだなと(笑)。
それは刈馬さんの経験に基づいているのですか。
■刈馬:全然基づいてない(笑)。ここは安全だからと行って。安全じゃなかったらどうすんだと。それは合コンと一緒だよと。やはり、理想なんですよ、どちらも。平和な世界であるとか、平和な日本。理想の社会を作るという大義名分で政治っていうものが行われていて、男女の付き合いというのも、愛を育むとか、愛こそ全てっていう理想や奇麗ごとに基づいている訳ですよ。だからどちらも白いシーツなんですよね。その白いシーツにインクを一滴垂らしたら凄い目立つからすぐに洗わなきゃいけない。だから、白であればあるほどそうだし、白であろうとすればするほど、次々と染み出てくるインクの染みが苛々してしょうがない。なんでこんなんなってるのか。いっそ燃やしてしまいたいとか(笑)。
作品を作るにあたって、チラシだとか舞台の照明、大道具、小道具、それらにも刈馬さんは大きく関わっていると思いますが、そういうところでこだわっているところはありますか。
■刈馬:ビジュアルコンセプトですね。チラシはデザイナーと相談しながらですけれども、舞台美術は基本的に全てぼくがプランニングしています。大事なことは、そこから世界が始まるように作る。開演時間になって世界が始まるのではなくて、その前段階からちゃんと世界が始まるものを作る。
チラシをぱっと見た時に、大体こういう感じのお話なんだと。
■刈馬:そうですね。それと同じように、お芝居が始まる前の30分の開場時間でもって、舞台美術を見せてることも同じことです。物語が始まる前に舞台美術を見てなにかを思い、なにかを感じることを共有したうえで物語を観てもらいたい。余韻の逆なんですけれども、ぼくは余韻のある作品を作りたいので。ここに出て来た登場人物たちはその後も生きていくんじゃないか、その人たちの人生が続いていくんじゃないかというのを思わせる芝居を作りたいと思っているので、その逆に物語が始まるまでの時間というものも大切にしたい。
ぼくの代わりにやってくれている人はいないので
刈馬さんが演劇で表現したいものはありますか。
■刈馬:単純にぼくがなにを面白がるかということ。ぼくよりも優れた作品はたくさんありますけれども、ぼくが一番観たい作品、世界、空気、というものは、ぼくの代わりにやってくれている人はいないので。クオリティだとかレベルの問題ではなくて。だからぼくは作り手で居続けられる。あとは、恋愛ものを多く取り扱うのですが、それはなんでかというと、人と人とが否応無く向き合うからです。今の社会では希薄な人間関係が多かったりするのに、恋愛というというのはいつの世も無くならない。人と繋がりたいという欲求が凄く強い。でも、人と人が一緒にいたら衝突が起こる。恋愛をただ描きたいのではなくて、なんで人と人は繋がりたがるのか。傷ついても傷ついても繋がりたくなるのか。というようなことを書きたくて恋愛を扱うので、それは自分の一番大事なところにあると思います。また、ぼくはなにかしらのコミュニティが崩壊する過程を描く芝居が多いんですが、結局人間は繋がり合えない。繋がり合えないんだけれども、繋がろうとするっていうのが、ぼくの中でのずっと変わっていない結論なんで。そこで諦める人間は書きたくないんですよ。それでも繋がろうとする。それが人間の悲しいところだし、それが生きるってことなんじゃないかと思っています。
最後に、今後テラ・インコグニタを、どのようなカンパニーにしていきたいと考えていますか。
■刈馬:できるだけ長く、そして精力的に活動していきたいと考えています。でも、ぼくがこうしたいああしたいというのは色々あっても、あくまで集団ですので。
メンバーによってもやりたいことが変わってきますよね。
■刈馬:メンバーが入ってくることで僕自身が影響を受けるでしょうし。ただ、意識的にメガトンロマンチッカーの時とは全然違う作品スタイルにしようとは思っておりません。変わるかもしれないし変わらないかもしれない。
始めてみないと分からないですよね。
■刈馬:集団というのは生き物だと思っていますし、自分だけのものではないと思っているので。そこを今から決めて固めるようにはしません。自分たちなりのテラ・インコグニタを目指すことだけは間違いないですけどね。
今後に乞うご期待ということで。
■刈馬:そうですね。
今日は長い時間ありがとうございました。
■刈馬:こちらこそ。