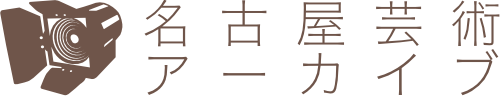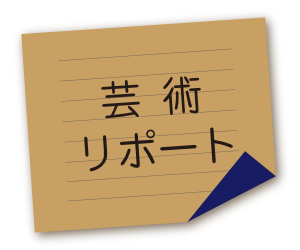演劇と関わるきっかけを教えてください。
■柴幸男さん(以下柴):高校に入ってから演劇部に。小さい頃からなんとなく、こういう仕事するんだろうなと思っていました。面白いことを考えられる人って凄いなって前々から思っていて。あんまり瞬間的に面白いこと考えられるタイプではないんですけど、じっくり考えてどうにかするならなんとかなるかなと。
書けるのであれば、舞台じゃなくても良かった?
■柴:目の前でやることに凄く憧れていたんだと思います。映画とかテレビだとリアクションがすぐに返ってこないんです。じゃなくて、目の前の人を楽しませるのが面白いなと思って。そう考えると演劇なのかな。演劇だ、とは思ってなかったけど、近いなとは思っていました。
大学に進まれてからは、どのように。
■柴:大学では放送学科に入ったんですけど、ここには演劇をやるつもりで入りました。わざと学科の違うところに入って、放送とかの勉強をしておけば、将来的にいいんじゃないかと思って(笑)。でもやりたいことは演劇でした。
その頃には劇団に入っていたんですか。
■柴:同い年の学生が立ち上げた劇団に旗揚げから参加して、劇団員に。
そこで脚本を?
■柴:はい。持ち回りで。作家志望の人が三人くらいいたので。
ドドミノは。
■柴:はい、その時のです。一時間半を越える戯曲を書いたのは初めてでした。
初めて書く一時間半の戯曲はしんどくなかったですか。
■柴:でもその時は、大学入ってすぐ演劇やりたかったんですけど、なかなかうまく演劇の人と知り合うきっかけがなくて。演劇学科じゃないので(笑)。割と芝居やりたくて仕方ない状況だったんですね。やりたい気持ちに溢れて仕方ない気持ちで書いたので、あんな苦労しないで書いたのはないくらいですね。
相当に勢いがあったんですね。
■柴:それでも一ヶ月くらいかかったんですけど、大本となるノートみたいなのがあるんですけど、それはもう一気に出来上がって、書く事で苦しいとかそういうことはほとんど覚えていないですね。唯一それは。高校の時に初めて書いたものは苦しんだ覚えがあります。
『仙台劇のまち戯曲賞』を穫って、そこから青年団へ?
■柴:穫ったのは大学四年なんですけど、一回就職してるんです。ADをやっていたんですけど、その頃は戯曲さえ書ければいいと、演出とかは考えていなかったんですけど、色々と忙しいので辞めました(笑)。自分のやりたいことやるのに時間がかかり過ぎるなって。
柴さんとお話していく中で「イメージの共有」を重要としていると感じたのですが、それを役者に意識させる為にやっていることはありますか。
■柴:もの凄い高いレベルで意識を集中することは重要だと思います。糸を紡ぐような作業なんです、演出というのは。それを続けて、糸がある程度乗ってきた時に、どんどんどんどん皆のイメージを引っ張っていく。皆で糸を紡ぎながらひとつの芝居を作っていく。ひとつの役を複数人でやることがあるんですけど、それはその複数人でひとつの糸を紡いでいく作業なんです。ブチって切って自分から糸を張り始めても駄目なんです。それを一時間半なら一時間半やるとして、この間やったのは、ひとりの女の人が歩く人生を描くという。十人が延々歩くんですけど、たぶん捌けで言うと、2〜300くらい。だから20回転くらいしている。1分に1回、もっと短いくらいで。でもあくまでひとりの人間を演じるんです。だから、そのうちの誰か一人でも息を途切れさせてですね、集中力を途切れさせてしまうと、イメージの共有が一気に崩れる。そう考えると、集中力と、もの凄い高い技術が必要とされる。
イメージの共有という言葉は、糸を紡ぐという作業の中から出て来た?
■柴:平田オリザがイメージの共有ということをよく言っていたんです。ぼくはもっともっとそれを引き出すことをしたい。『反復かつ連続』では一人の人が五人姉妹を演じていて、一人しか舞台上にいないのに、もの凄く精密に間をとって合わせて、動きも重ならないように気を配って、ぶつからないように、ちゃんと動き通りやると、どんどんどんどんイメージが増幅していくんですね。観た人がイメージを重ねていくんです。姉妹の役に。舞台美術はなにもなくて、イメージの共有ができなかったら単なるスカスカの舞台に見えるんですが、それができると、お客さんが朝食のイメージ、かつて食べた朝食のイメージをそこに投影して勝手に楽しんでくれるんです。本来なら誰がみてもこの朝食風景は懐かしいなという芝居は無理。人それぞれによって違うから。でも、こっちでそれを計算して、イメージを共有させていくんです。そして、イメージの共有の更に上にいくと、想像力の増幅というか、共有を越えて更に高いレベルまでイメージを積み上げられるんですね。お客さんと舞台が。
高いレベル?
■柴:嘘くさくない感覚から、更に自分のこれからの未来と現在と過去とを勝手に想像して観始める。そして、逆に今度はお客さんのほうからもイメージを出してきてくれて、それに舞台が引っ張られる。もうひとつイメージのレベルが上がる。これをもっと面白がってやっていこうかなって。
最初は舞台から投げたものを、イメージが増幅していくと客のほうからも返してくれる。
■柴:そうですね。一個の固まりになるんです、舞台上と客席が。井上ひさしさんは「観劇の共同体」とか「演劇の共同体」とか言いますけども、客席全員と舞台がうねるような形になってくるんですね。ひとつになって。もう、切れ目がない状態になってくるんです、舞台と客席というのが。なんか別のひとつの固まりになって、更に共有が高くなる。
この状況は柴さんの演出では見られますか。
■柴:(笑)。出来る時と出来ない時があります。集中力が切れる時とか。むしろお客さんとの共有関係かな。うまくいかない時はうまくいかない。
それは客のコンディションに左右されるものでしょうか。
■柴:お客さんのコンディションが悪くて舞台が悪くなることはあんまりなくて、舞台が悪いけどお客さんが乗ってくれたということはありますね。客席のせいで舞台まで落ちるということはあまりないですね。大体舞台上が駄目になってうまくいかなくなります。
それは役者がイメージの共有を出来なかった?
■柴:それもあるけど、戯曲的にここが弱いとか、弱点があったりすると、そこから崩れていきます。それをさせない為に事前にもっとぼくが準備するべきなんです。でも、そこまで作ってもコンディションが悪くなることもある。
柴さんが必要とする役者の条件を教えてください。
■柴:舞台上できちんと会話ができること。それに加えて、「負荷」というんですけど、わざと負荷をかけて自然な会話にさせる。ここを越えるなって歩かせて、それをしながら時計を見てくれとか。負荷がかかってくると逆にどんどん自然に台詞が言える。そしてその負荷自身も表現になっているんです。皆が同じ速度で、一人が右足で出た瞬間に、もう一人が右足で入ってくるという、これは負荷以外のなにものでもない。これをしながら会話劇をやる。これが出来ると、一人の人間が喋り続けながら歩き続けているようなイメージが出来上がる。これをやる為に必要な条件というのは、「これを言って」と言われて言える能力は基本で、そういう作業をしながら、右足で出た瞬間右足で入る。八歩なら八歩で必ず歩いて、右足でもう一回出て、それまでに台詞を終えて次の人にバトンタッチする。この難しい作業を全部こなして、更に、そこの台詞は一秒間を空けてとか、ここはこういう風に言ってとか、それが出来る人。
負荷をかけることで自然な台詞が出るという話でしたが、でも一方で、楽な姿勢で台詞の読み合わせをすることがありますけど、その意図は。
■柴:それはぼくじゃなく平田オリザのやり方ですけど、要は意識の分散。台詞をうまく言おうとする意識を取り払ってあげればいい。うまく言おうとするとどうしても力が入って、演技っぽくなってしまうので、負荷をかけた場合は台詞に構っていられなくなる。リラックスさせた場合は、肩の力を抜かせて、うまく台詞を言おうと思わせなくする。
根本にあるところは同じことなんですね。
■柴:そういうことです。負荷のほうはギチギチにして考える暇をなくすこと。リラックスさせるのはポカーンとさせてそもそも考えさせなくする(笑)。
自分なんかは句読点にこだわってしまうタイプなんですけど、中には状況に応じて変える方もいますよね。その辺はどう思われますか。
■柴:句読点は全て計算して書かれているので、それはその通りに。でも、演出すれば点が打ってあるところは自然と分解されると思います。最近言われていることですけど、字の形を見て喋るというのはそもそも違うんですよ。だから覚えてくれってぼくは言うんですけど。青年団の稽古は、稽古開始の時には皆台詞を入れてるんですね。そうしないと稽古にならなくて。字の形を見て喋るということは、普段喋っていることと近いレベルにあると思っている人が多いと思いますけど、全然違うことなんです。字を書く事に近いかもしれない、字を読むことは。台詞を身体の中に全部飲み込んじゃって、それを舞台上で再現すれば、点とか丸の位置は書いた通りになると思います。
役者はあまり正確な台詞回しにこだわる必要はない?
■柴:……という気持ちで役者はいたほうがいい。あくまでも劇作家としては書いた通りに。演出家としては、多少は役者が言いたいように変えてもいいだろうと。だから演出家と劇作家のせめぎ合いですが、でも、どうしても変えちゃいけない言葉とかあったりして。演出家から見た時にも。語尾くらいは変えてもいいですけど、変えないで自然に言うのが一番いいですね。
やはり脚本家としては、本の通りにやって欲しい?
■柴:大切なのは、場が成立しているかしてないかっていうことなんです。コンテクスト(※1)の話が分かった段階で、譲れない部分と譲ってもいい部分が明確になったんです。
コンテクストのことを知るまでは。
■柴:ぼくが頭に描いた通りになんで言えないんだろうって。そしてそう言ったほうが面白いと思ってたんです。でも化物みたいな役者もいて、その人がさも考えたように喋る人もいるんですね。多少の稽古は必要なんですけど、掴みさえすれば。どんな台詞でもとは言わないですけど、おおよそ普通の人がやったのでは成立しえない、その人が喋ってるようには思えない言葉を言う人たちがいます。
化物みたいな人ばかり集めて芝居してみたいと思いますか?
■柴:必ずしもそういう人たちばかりで面白い芝居が作れるとは限りませんから。逆にねばってねばって最後に出すパターンの人もいるんですね。そういう人の魅力もあるので。左門豊作的な。花形タイプもいれば、左門タイプも。時間かかる人もいるんです。
自分が柴さんとお話していて一番感じたのは間を大事にする人だな、と。こだわりはありますか。
■柴:なんとなく間を使うことはやめてるんですね。全部計算していて、ここで何秒間空くとか、それは演出家の視点ですけど、お客さんのイメージの共有の為の時間なので、そんなに長く空けても、それ以上想像することはないという時は短くしてと言うし、そんなに短くするとせっかく共有が生まれ始めていたのに、そんな先にすぐ行っちゃいけないとか。間というのはそういう風に使う、想像力をうまく表現する為に使うんです。喋っている台詞に合ってる間違ってるとか言いますよね。それと同じことが空白にもあるということです。空白だから良い悪いの境界線が曖昧ということは全然なくて、無言が喋っている状態なんです、それは。空間が喋っていると言ってもいいんですけど。誰かが異常にゆっくり台詞を言ったり、間延びしたりして言ったら、それ長過ぎるとか遅過ぎるとか、分かりますよね、皆。それと同じこと。
今後の演出活動について考えていることはありますか。
■柴:職業演出家になることはないですね。ちょっと演出もできる劇作家になりたい。人の戯曲を演出して回ることはないと思う。
そのように考えるきっかけがあったのでしょうか。
■柴:もっと面白い人たちがいるので。
戯曲を書くうえで、演出の技術も必要だと思いますか。
■柴:短絡的にはそのほうがいいと思っていたんですが、もの凄い長期的な目で見れば、関係ないと思う。もしかしたら演出の目なんかない劇作家のほうが凄い作品を書くかもしれない。どう見せるかを考えるのが演出家なんです。あんまり演出をやっていると無難なことしか書けなくなってくると思う。頭の中で「これは無理だ」ってことを最初から切り落として書かないようにしないといけない。でもきちんと売れてる方は使い分けてる。戯曲を書くときは演出家にならないように。最近ぼくはどう見せるかを考え始めちゃっています。書きたいように書くのが劇作家なので。でたらめに書くのが。敢えて妄想を止めるようなことをしてしまう。突き抜けなくなってきてしまう。分かった、どうして最近うまく書けないのか(笑)。
いま分かったんですか。
■柴:いま分かった(笑)。
インタビューした甲斐があったというものです(笑)。
■柴:戯曲を書く時には書く事だけに集中して。どう舞台にするとか考えちゃ駄目なんです。
今後、演出活動はされていきますか。
■柴:ちょっとはしていきます。それが一番面白いかどうかは別として、自分の作品を自分で演出するのが仕事的には早いはずなので。それが最も優れた作品になるかどうかは別ですが。
自分以外の演出家に不満があるとか。
■柴:そんなことはないですよ。誰がやっても不満になると思うんです。どんなに凄いバージョンを作られたとしても、ぼくとしては不満でしょうね。劇作家としては。不満というか、ここはこうじゃないのにとか、思うに決まってるんです(笑)。その通りにやったほうが面白いか、別の演出家がやったほうが面白いかは別問題なんです。単純になんで自分でやり始めたかというと、人に説明してられなくなったんです。でも、逆にそれのせいで演出家の脳になってきてしまった。ミイラ取りがミイラになってしまった。
戯曲で描きたいものはありますか。
■柴:一瞬でもいいんですけど、過去と現在と未来の全てを感じるような、観たような感覚を得るような作品を作りたいです。それは心がけています。これがちゃんと紡がれている作品が名作と呼ばれるんじゃないかなあと気付いたんです。ようは、過去こうだったでしょ、現在こうだったでしょ、未来はこうだったでしょ、と、押し付けるとテーマになる。単なる主義主張になってしまうので。じゃなくて、先ほどの共有と同じで、お客さんが観た時に、瞬間的にどこでもいいので、かつてわたしたちはこうだったのかもしれない。今わたしたちはこんな感じかもな。これからわたしたちはこうなっていくかもしれないな。ぼくのこれまでの経験上、どうやら名作、傑作というのはこれらが全部がある。過去、現在、未来。
ひとつの作品の中に全てがある。
■柴:はい。それを傑作というらしい。
具体的な作品名とかありますか。
■柴:ロミオとジュリエットとか、長くやられている作品なんかはそうだと思いますよ。何百年も堪える芝居ってそうなんですよ。現在だけを切り取ったら保たないんですよね、時間に。でも、遠い百年後を描けば百年持つということでもないんですよ。現在、過去、未来を超越しているから保つんですよね。超越しているというか、どれもある。どこでもない時間軸の座標にあるんです。
どのようにしてこのことに気付かれたんですか。
■柴:同時代性と普遍性ってものを考えたんですね。名作っていうのは簡単に言ってるだけなんです。同時代性と普遍性を両方持つ作品のことです。同時代性というのは現在、普遍性というのは過去と未来。両方あるのが名作と呼ばれると思う。
国や文化が違う場合には。
■柴:それでも通用するものだと思います。それこそそれを越え始めると純度が高くなる。純度が高くなれば、同時代性、普遍性を持っていれば、どこの国であろうがどこの時代であろうが通用すると思います。
そういう作品、作れそうですか。
■柴:一人一作くらいじゃないですかね。作れるのは。
今日は本当にありがとうございました。
■柴:こちらこそありがとうございました。